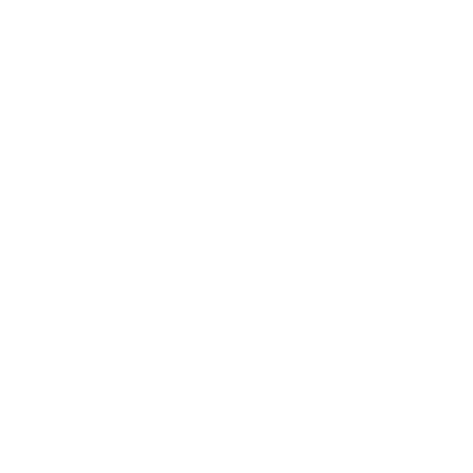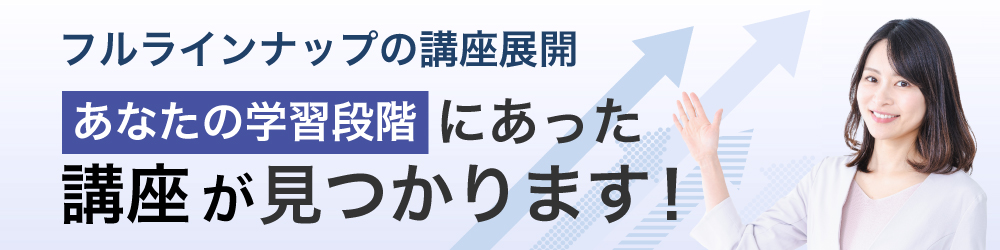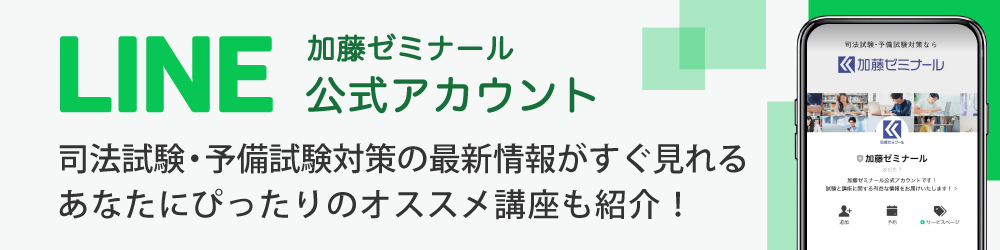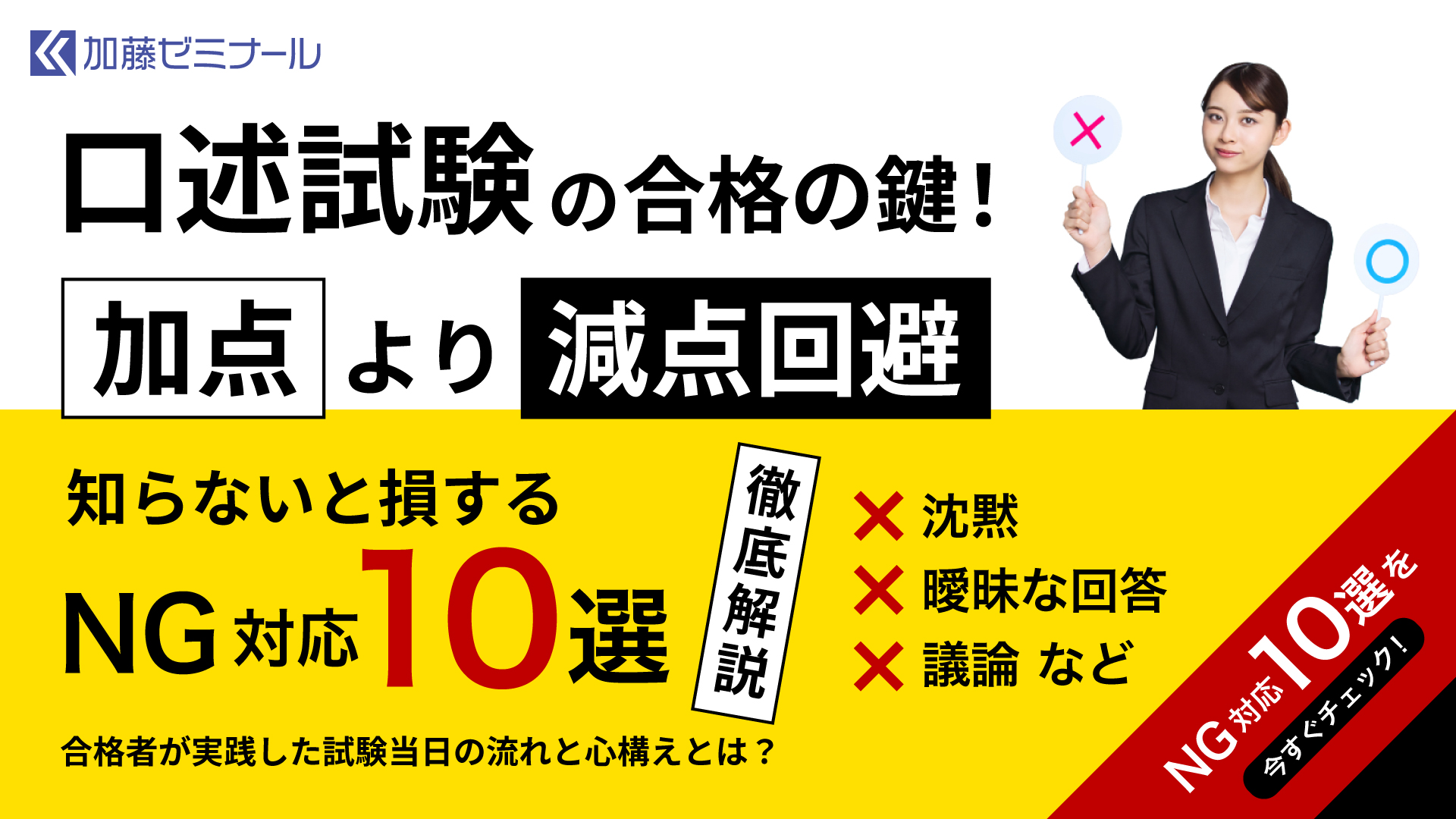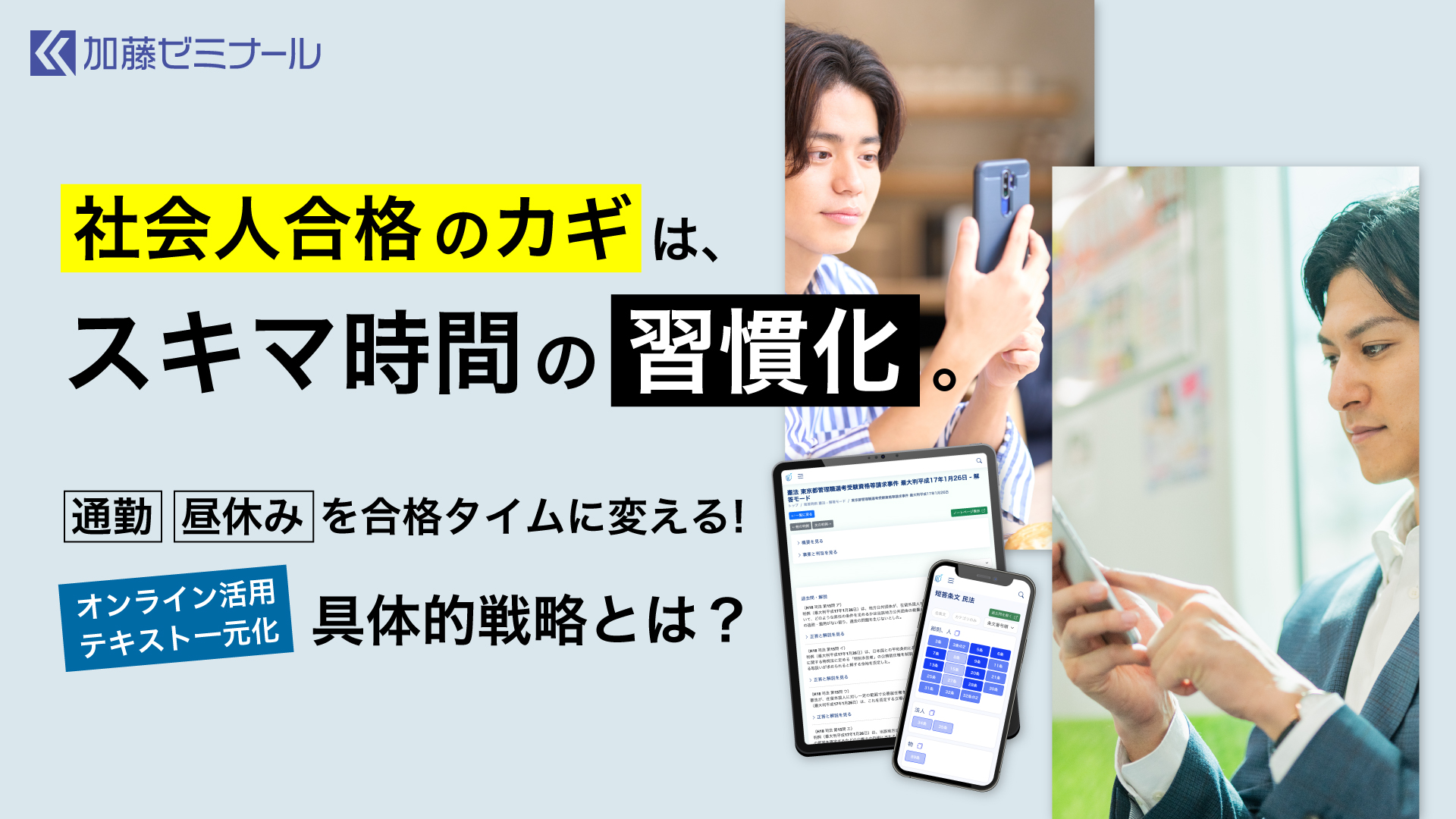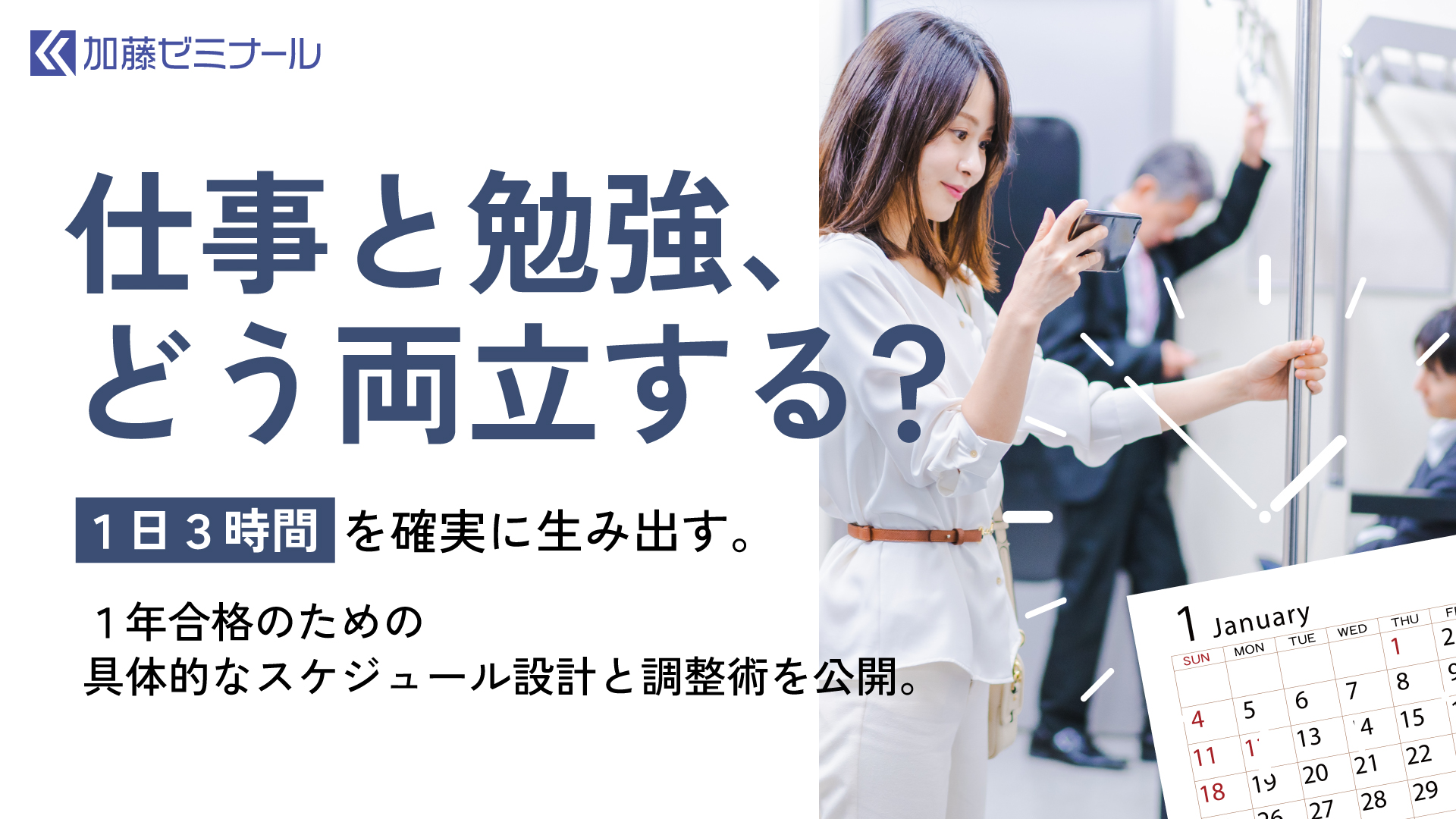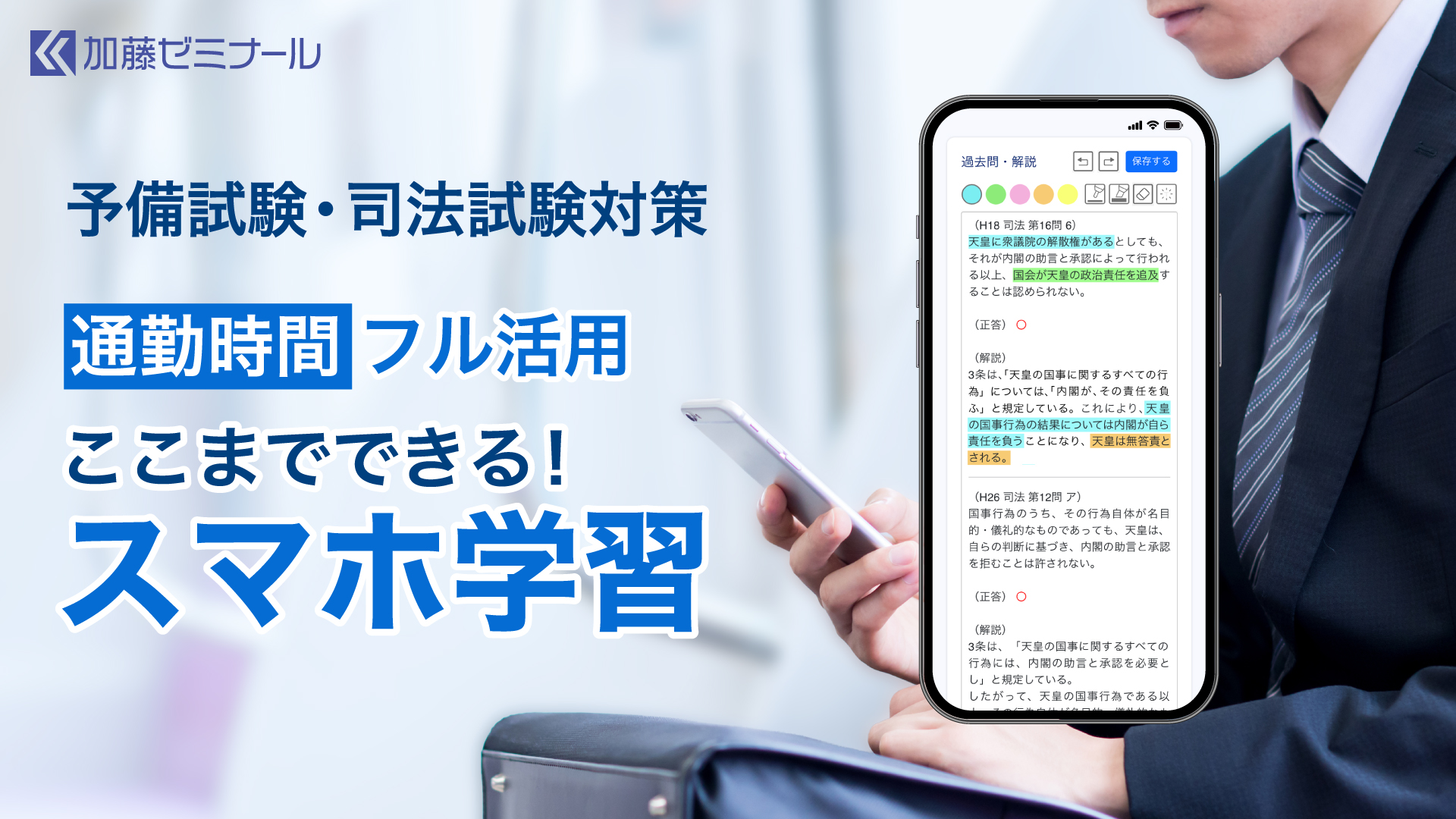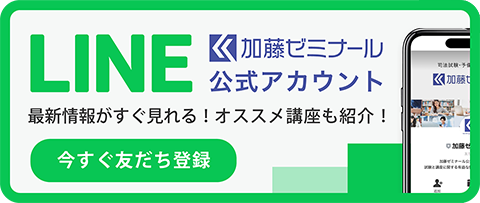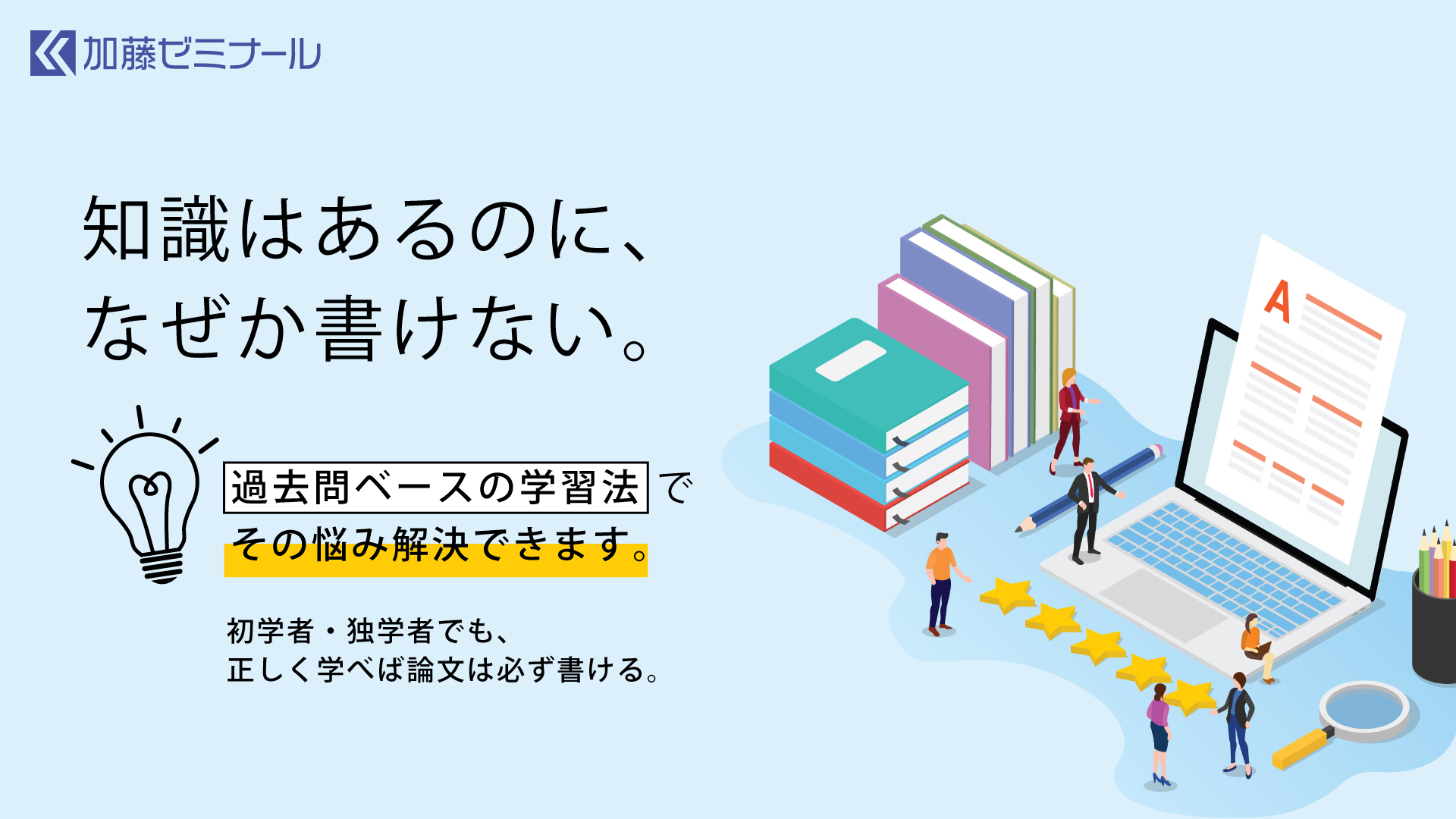
Contents
予備試験の論文式試験が不安な受験生へ~過去問をベースにした最短合格術~
「論文式試験が不安…」「知識は入っているはずなのに、答案が書けない」
司法試験予備試験を目指す多くの受験生が、論文対策でつまずきます。予備試験における天王山は、論文式試験だからです。
本記事では、過去問を中心に据えた論文学習法を軸に、合格に直結する実践的ノウハウをお届けします。特に、どのように学習すればいいのか分からないと悩む初学者や、独学で不安を感じている社会人にこそ読んでいただきたい内容です。
論文式試験を「不安」に感じる理由
論文式試験を「不安」に感じてしまう最大の理由は、正解が見えないことにあります。
確かに、短答式試験のように明確に正誤が決まっているわけではなく、単純に知識だけが問われるだけでもなく、その結論に至るまでの思考力や文章力が試される試験であるため、自分の答案が現在どれくらいのレベルなのか、本試験で評価されるのかが分かり難いという側面があります。
また、そのような中で迷いや不安を抱えながら学習をしていると、モチベーション維持も困難になりますし、学習効率が悪くなります。
本記事では、少しでもその不安を取り除けるように、論文対策のための学習ノウハウを提供します!
予備試験合格のための学習の肝は、インプットとアウトプットの高速往復!
予備試験対策の学習の肝は、インプットとアウトプットの高速往復にあります。
知識を詰め込む(インプット)だけでも、問題演習ばかりする(アウトプット)だけでも不十分です。両者を行き来しながら、知識を使える形で身につけることが、合格への最短ルートです。
たとえば、論文過去問を解いた後に、この論点は知識として定着していなかった、規範は覚えていたが当てはめが弱かった等と気づいたなら、その部分を重点的にテキストで確認・整理しましょう。
このように、インプットとアウトプットの往復作業を日々高速で繰り返すことで、知識を答案の形にするための実力を効率的かつ効果的に身に付けることができます。
過去問は最良の教材
論文式試験の対策において、最も効果的で、かつ信頼できる教材が「過去問」です。
過去問は、単に過去に出題された事実関係・問われ方を確認するためだけのものではなく、出題趣旨・採点実感には「出題者の意図」が凝縮されています。
基本書等も大切ですが、これらはあくまでも試験で問われる法律知識をインプットする段階で重宝されるものです。他方で過去問は、インプットした法律知識を答案でどう使うと得点に繋がるのかという、「合格」に直結する情報が詰まった教材であるといえます。
したがって、過去問に繰り返し取り組み、出題パターンや主題者の意図を理解することが、合格への最短ルートです。
なお、これらの学習をするために、すべての過去問の出題者の意図やその推移等を自分でまとめ上げるのは非常に困難ですし、効率も悪いです。
加藤ゼミナールのアウトプット講座では、過去問における出題趣旨や採点実感について徹底的に分析し、どのようにアウトプットすると本試験で評価されるかという合格への結論を明確に示していますので、是非活用してみてください!
過去問演習→インプット強化の黄金ループ
ここで紹介する学習方法が、過去問演習→予備校の解説確認→自分の弱点抽出→重点的なインプットのループです。先に説明したインプットとアウトプットの高速往復の具体的な内容です。
これは短答対策と論文対策の双方に共通する、合格者が実践している王道の学習法です。
【学習サイクル例】
①論文過去問を制限時間内に解く
.②自分の答案を模範答案と照らし合わせて、「自分の抜け」を特定
.③抜けていた条文・規範・論点をテキストで重点復習
.④同様の論点が出る別の過去問で再アウトプット
このサイクルを1日1問ペースで回すだけでも、アウトプットする力とインプットによる知識が並行して伸びていきます。
合格答案レベルの把握が、最短合格の鍵
論文式試験において、どのレベルの答案で合格できるのかを知らずに勉強するのは、何を作るのかを決めずに材料を調達するのと同じです。
そのため、まずは予備校などが提供している模範答案を参照し、自分の目指すべきゴール(=本試験の日に、どのような水準のアウトプットが出来ていればよいか)を明確にしておきましょう。
解答の型となる答案の構成、各論点に対して展開すべき自説、文体や分量など、模範解答から学べることは非常に多いです。
特に初学者は、限られた本試験までの間に、どの水準までであれば達することができるのかといった目標ラインについて、模範解答を通じて設定しておく必要があります。
模範解答を使いこなす:加藤ゼミナールの活用術
加藤ゼミナールでは、一部模範答案として中上位合格レベル・超上位合格レベルの2段階で提供していますが、これは上記のゴールの設定のためにとても有益であると合格者からも非常に好評です。
この2段階の模範解答を活用することで、
・現時点の自分のレベル(=現在地)…合格答案と自分の答案との間にどれだけの差があるか
.・合格するために必要な水準(=目標地点)…各水準の合格答案にどれだけのことが書かれているのか
を明確に確認し、設定することができます。
中上位答案は合格するための最低限を押さえた実践的な形、超上位答案はトップ層での合格を目指すための完成形として参考にできます。
このように、合格水準の見える化がされている教材を活用することで、自分の学習の方向性と必要量を見極めることが出来ます。
まとめ:過去問こそ論文対策の王道
論文式試験は、正しく学習すれば必ず攻略できます。
問題文が長く、予備試験では時間も短く感じるかもしれませんが、過度に不安になる必要はありません。
大切なのは、以下のポイントを確実に押さえることです。
インプットとアウトプットの高速往復を繰り返す
.過去問をフル活用する
.演習後に弱点を明確化し、重点的にインプットする
.予備校の模範解答を使って、現在地の確認と目標設定をする
過去問は最良のテキストの一つです。そして、過去問を「戦略的に活用する技術」こそ論文合格の鍵です。
加藤ゼミナールは、過去問を活用したカリキュラムと、実戦的かつ段階的な模範答案を通じて、あなたの論文式試験対策を全面的にサポートしてくれます。
不安を乗り越え、予備試験が解けるようになっている自分へ。
今すぐ、一緒に一歩を踏み出しましょう!
実務家弁護士T
社会人受験生として学習期間1年で予備試験に合格し、翌年の司法試験には、総合31位・オールAで一発合格