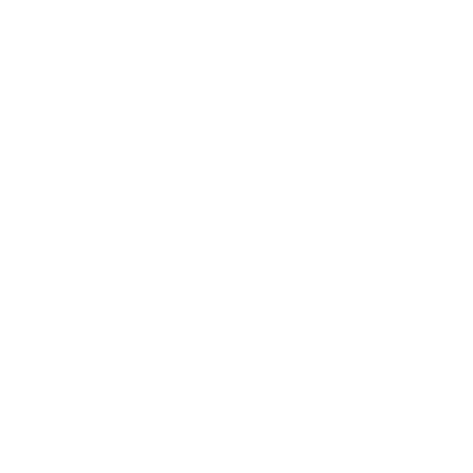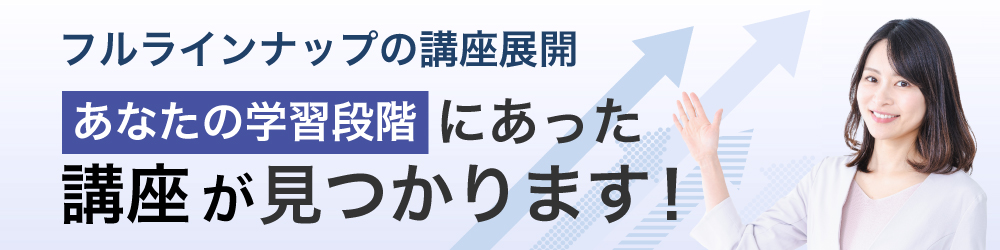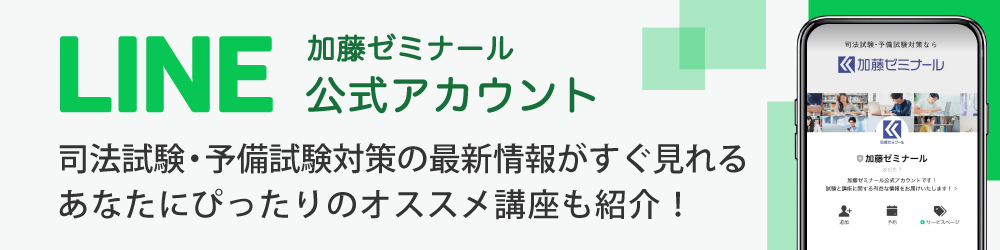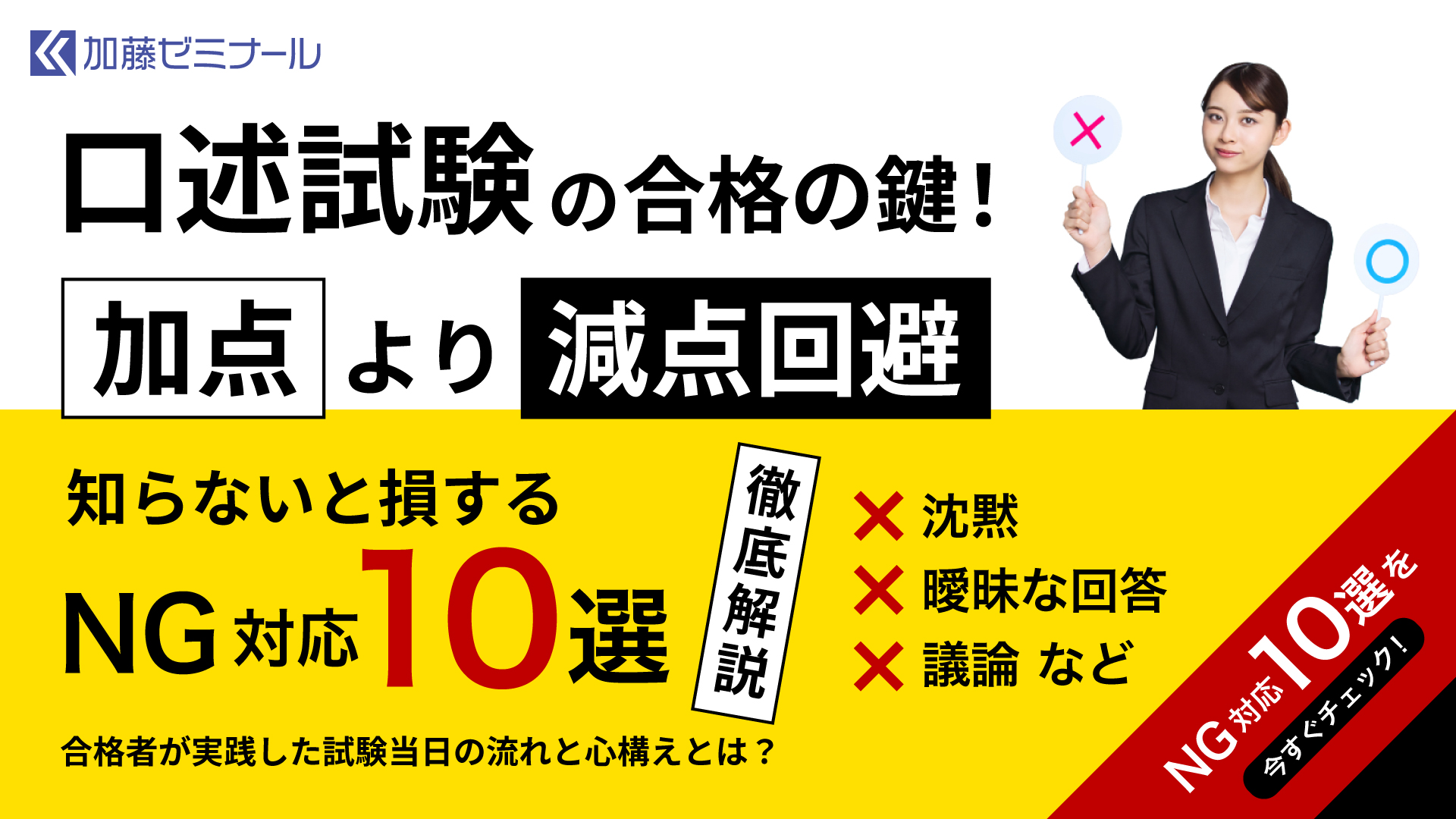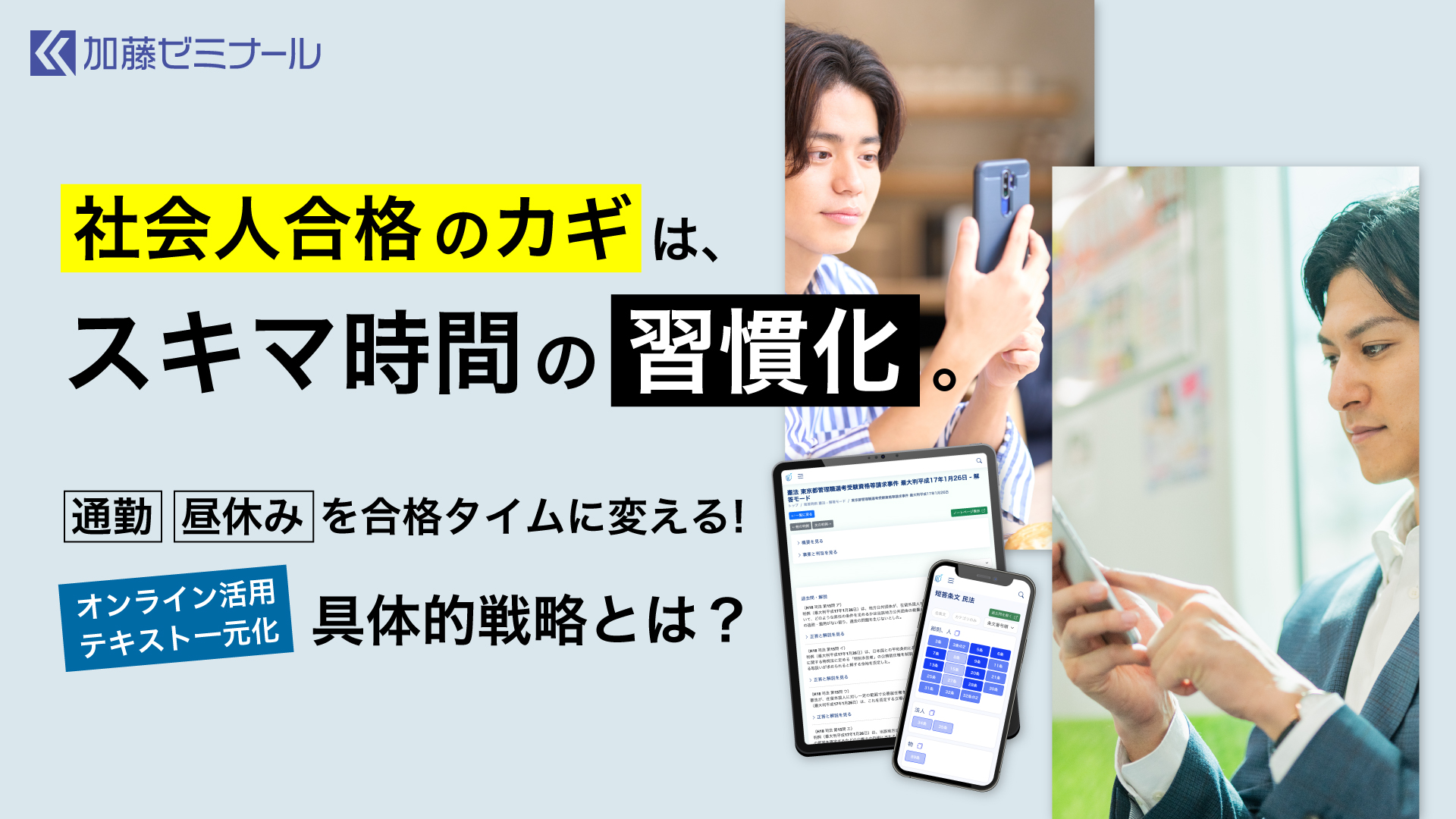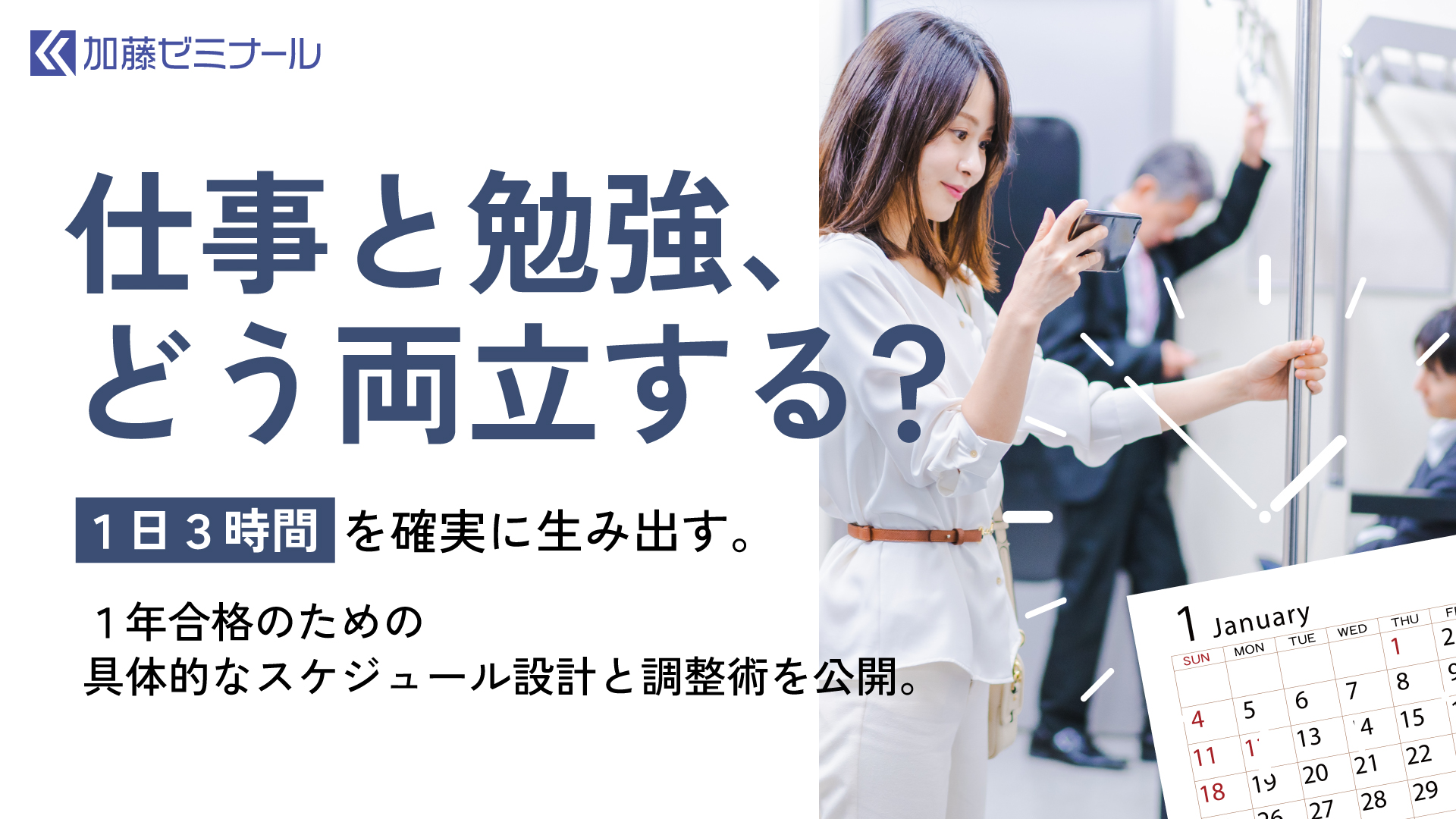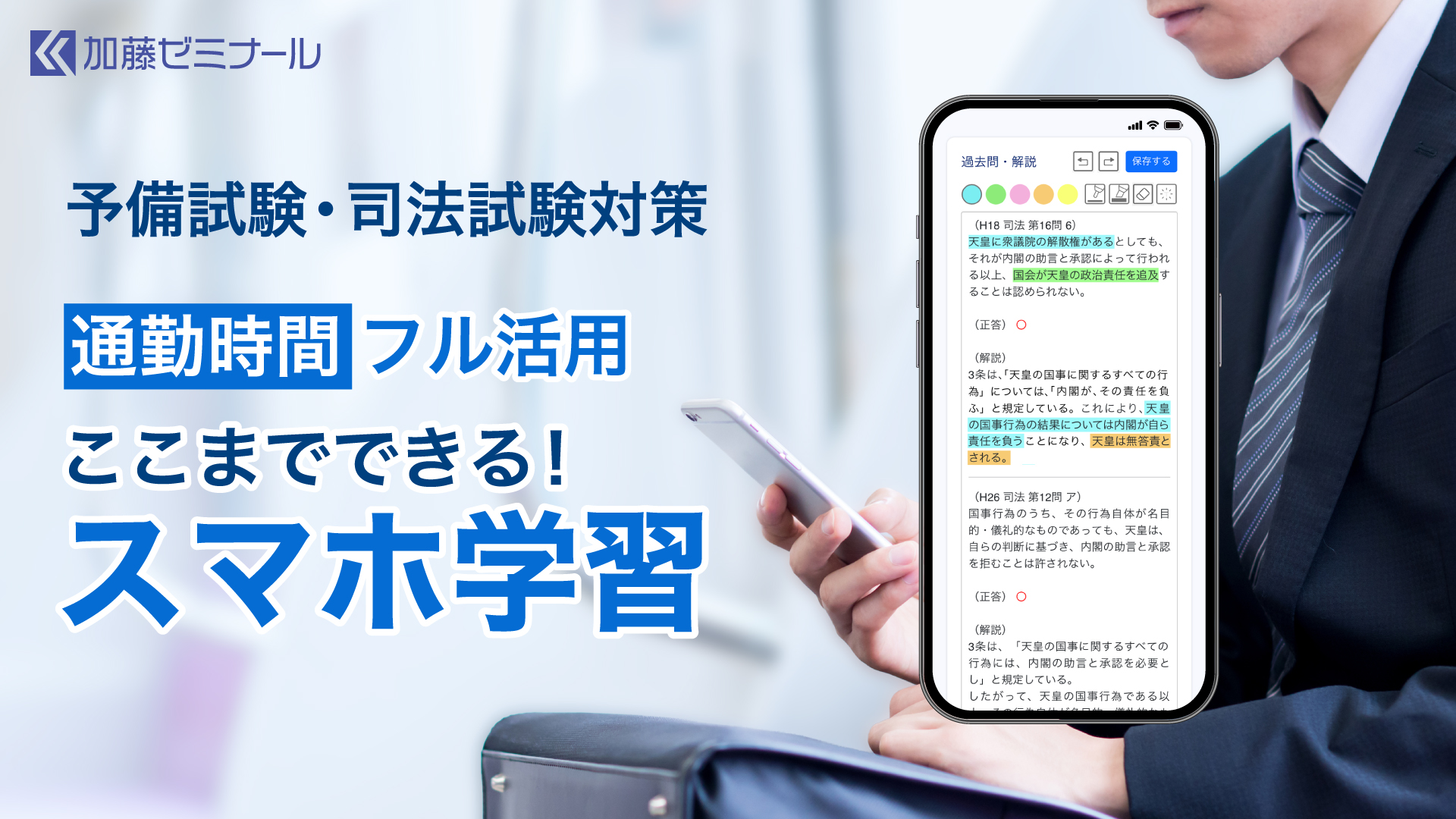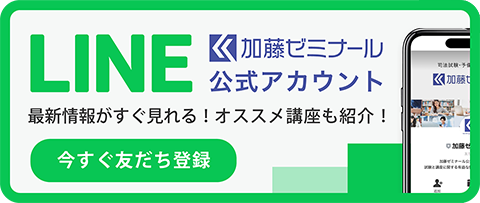Contents
公法系・民事系・刑事系の学習順序はどうするべき?‐社会人合格者の戦略と柔軟な学習アプローチ-
「どの科目から始めればいいか…」
初学者を中心に、予備試験・司法試験を目指す受験生から非常に多く寄せられる悩みの一つです。
・公法系(憲法・行政法)をまとめてやるべき?
・まずは民事系(民法・商法・民事訴訟法)を一気にやるといい?
・刑事系(刑法・刑事訴訟法)は最後…?
このように、特に初学者の方などは、学習する科目の順序に悩んでしまうという人も少なくありません。
この記事では、「私自身がどう学習を進めたのか」を一例として、順序に囚われすぎない柔軟な戦略・学習を継続させるための工夫について、社会人合格者の立場から解説していきます。
学習順序に正解はない:戦略の前提にある柔軟性
まずはっきりと申し上げたいのは、この順序が絶対に正しいという学習の型は存在しないということです。
確かに、ある程度体系的に理解しやすいといわれている学習順序はあります。憲法はすべての法の前提となるものであるから最初に学習すべき、民法は全科目に共通する思考・論述の作法を学びやすいから最初にやっておくべきなど、さまざまな意見がある領域だと思います。
しかし、予備試験・司法試験の合格を本気で目指す場合、学習順序は中長期的な学習スケジュール全体から見ればその一部であるスタート地点にすぎません。
どの科目から勉強を進めても、結局は全科目を習得する必要がありますし、最終的にはある種全科目ごちゃ混ぜの状態で学習できる状態まで持っていくことがゴールだからです。
私が選んだ学習順序:憲法→民法→商法→刑法→民訴→刑訴→行政法
私が実際に採った学習順序は以下の通りです。
憲法 → 民法 → 商法 → 刑法 → 民事訴訟法 → 刑事訴訟法 → 行政法
特に明確な意図があったわけではなく、予備校における教材の並びや心理的なハードルの低さ(憲法や民法は大学[非法学部]の授業でも触れたりしていた)を基準にして選んだ結果です。ご自身が利用している予備校があれば、その予備校が推奨している学習順序に従いましょう。
また、大きく言えば、実体法から手続法へという流れは分かり易くなることが多いと思われます。実体法を理解していない状態では手続法を理解しにくい箇所も少なくありませんから、実体法→手続法という流れは守ったほうがいいです。
もっとも、訴訟手続に興味があったり、知見がある方等は学習の入口としてとっつきやすいところから始めるという意味で、手続法から学習するというのもあり得る選択であるとは思います。
繰り返しになりますが、どれから始めても、後で必ず全体をカバーし直すことになるからです。
インプットとアウトプットを初期から並行させるのが鍵
重要なのは、科目の学習順序よりも学習の構造です。
私の場合は、例えば憲法の過去問を解いている(アウトプット)時期に、並行して民法の講義を視聴する(インプット)等といったように、科目横断でインプットとアウトプットを並行していました。
この並行学習によって、インプットだけ・アウトプットだけといった形で偏りを生まずに、常に両者の学習が行われていることで、双方の能力と肌感覚が継続的に養われて、定着が図れました。
学習初期段階から、知識習得(インプット)→知識を使う=問題を解く(アウトプット)→間違えた箇所を復習(インプット)→知識を再度使う=問題を解く(アウトプット)…という往復運動を学習の構造とすることで、成長を加速させることが重要です。
1週間の中に複数科目を組み込む利点
まずは、憲法だけをひたすら集中して1週間やり続けるというようなやり方も可能です。
しかし、予備試験・司法試験の実際の試験や直前期の学習では複数科目についての知識を短期間で処理する・詰め込む対応力が求められます。
だからこそ、早い段階から短期間で複数科目について脳が作用する状態を作れるようにしておき、複数科目をバランス良く回す感覚に慣れておくことは大きな武器になります。私は、1週間くらいの短期的学習スケジュールにおいて、なるべく複数科目を並行して学習することを意識していました。
この学習方法によって、ある科目を学習してから、またその科目に戻ってくるまでの復習のタームが短くなるため、記憶も定着しやすくなったと思っています。
まずは学習の第一歩を踏み切ることが大事
予備試験1年合格を目指すならば、講義を受けたり、テキストを読みという単純なインプット期間は全体の1/3程度にとどめるのが理想です。
残りの2/3は、復習とアウトプットの高速往復が中心になります。
つまり、どんな順序でインプットを始めようが、最終的には全科目を繰り返し回すフェーズが重要かつメインなのです。
順序に悩んで学習が進まないくらいなら、まずは手に取りやすい科目から始めてみましょう!最初に学習した科目のせいで全てを無駄にするということはまず無いと言えます。
とにかく止まらずに前に進むこと、学習に着手してみることを最優先にすべきです。
もう既に、本試験までの学習期間の時間の針が動き始めているからです。
モチベーション維持のための息抜き科目
私の場合、民法をやっていて条文の多さや範囲の広さに気疲れして、民法学習のモチベーションが下がりかけることがありました。
そんなときは、あえて息抜きとして、当時好きだった刑法の勉強に切り替える(一旦民法から離れる)、という方法を取っていました。
これは非常に効果的で、好きな科目・比較的得意な科目をリフレッシュとして挟むことで、全体の学習を継続しやすくなります。
順序通りやらないとダメだという思い込みは不要です。
モチベーション維持による学習の継続こそ、試験合格に最も重要なことです。
横断的な学習意識が現場力を鍛える
科目横断の学習意識も非常に大切です。
たとえば、民事訴訟法を勉強していて「この契約の場面、民法だとどこが問題になるだろう?」と思ったら、そのまま民法に戻って確認する。
こうした行き来を柔軟に行えるようになると、各科目のつながりが自然と頭の中で整理され、応用力が身につきます。
試験は確かに「科目別」ですが、出題される事案は現実の問題と同様、複数の科目の視点が交錯します。
だからこそ、今はこの科目だから他は見ないという姿勢はやめてみましょう!
ある科目を学習しているときに、「この場面、あの科目だと何が問題になるかな?」などといように、他科目の視点も取り入れて考える習慣を、ぜひ意識してみてください。
本試験に対応するための問題発見能力を鍛えることに繋がります。
まとめ:順序にとらわれず、動きながら最適化を
予備試験・司法試験の学習において、科目の学習順序は最初に気になるポイントです。
しかし実際には、その順序が合否を分ける決定打になることはほとんどありません。
むしろ重要なのは
- インプットとアウトプットを並行させて学ぶという構造
- モチベーションを維持できる柔軟な順序調整
- 息抜きとして得意科目を活用するといった柔軟性
- 科目横断的な視点を持った学習
- 学習を継続できる習慣と設計を身につけること
迷ったときこそ、まずは始める。
走りながら、軌道修正していけばいいのです。
合格は、完璧な順序で学習した人ではなく、止まらず学習し続けた人がたどり着きます。
あなたも、自分なりのやり方で、前に進んでください。
実務家弁護士T
社会人受験生として学習期間1年で予備試験に合格し、翌年の司法試験には、総合31位・オールAで一発合格