弁護士加藤 駿征
加藤ゼミナール専任講師
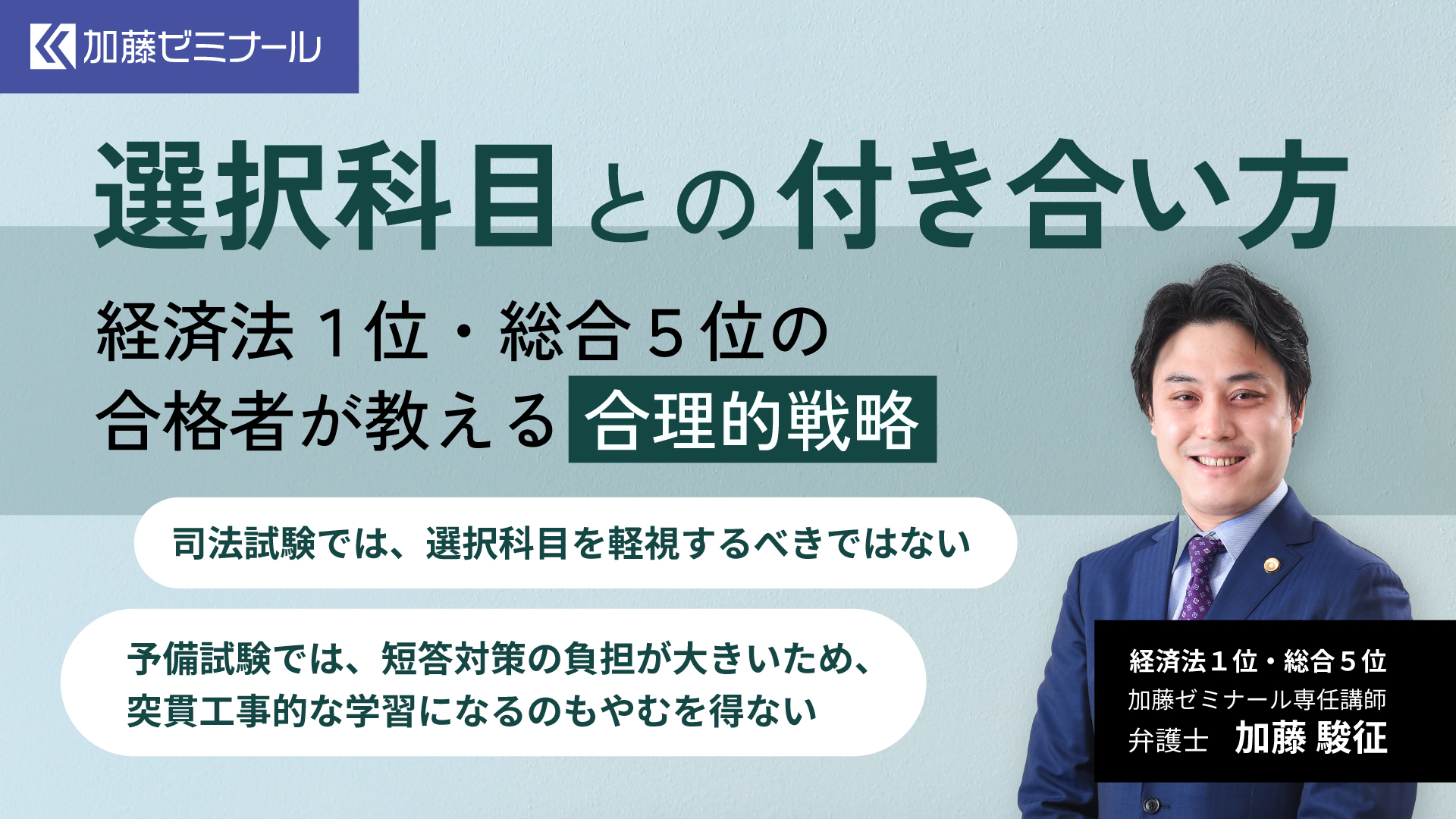
受験生の方からは、選択科目までは勉強が回らないとの話を聞きますので、今日は、選択科目との付き合い方に関する私の考え方を述べたいと思います。
.
1.司法試験における選択科目対策
私は、司法試験対策においては、選択科目を軽視することは避けた方がいいと考えており、その理由は以下の点にあります。
(1)配点は基本科目と変わらないこと
仮に、選択科目の配点がほかの基本科目に比べて低いとのことであれば、選択科目の学習に対するプライオリティを下げるのは戦略としてはありうるとは思います。
しかし、皆さんもご存じのとおりですが、選択科目の配点はほかの基本科目と全く同じ100点が割り振られているので、このような観点からは選択科目の学習のプライオリティを下げることは全く合理的ではないことになります。
(2)受験生のレベルが基本科目に比べて高くないこと
選択科目については、受験生が学習を始めるタイミングが比較的遅い傾向にあります。
私も経済法の勉強を開始したのは、ロースクールの2年生(私はロースクールでは、未修コースで入学したため2年生と表現しますが、既修コースの方の1年目に相当すると考えてください。)の後期になって、授業を取り始めてからですので、司法試験の受験までは1年半程度しかなかったことになります。
このように、ほとんどの受験生は選択科目については短い準備期間で司法試験に臨むことになりますので、受験生のレベルは基本科目と比べると相対的に低い傾向にあります。
裏をかえせば、周りのレベルが低い分、自分が学習を進めれば、差をつけやすい科目といえますので、ほかの科目よりも上位といわれる60点を取りやすい、コストパフォーマンスが高い側面もあるのではないかと考えています。
.
2.予備試験における選択科目対策
上記とは異なり、予備試験対策においては、選択科目のプライオリティを下げることは戦略としては合理的な側面もあると考えています。
なぜなら、予備試験においては、司法試験よりも短答試験の学習に多くの時間を割くことが求められると考えられ、短答科目にない選択科目については学習のプライオリティを下げざるを得ない部分もあると考えるからです。
司法試験とは異なり、予備試験では短答試験の科目が一般教養科目も含め、8科目あり、科目が多いので、受験生は司法試験に比べて、短答対策に多くの時間を割いていると考えられます。
また、予備試験については、短答試験の合格者のみが別日に論文試験を受験することになっており、受験生は短答式試験が近付けば短答対策をメインに据えると思われますので、その観点からも司法試験よりも短答対策に割く時間が長くなりがちです。反対に司法試験においては、短答試験と論文試験が同タイミングで実施され、かつ、短答は配点が低いので、試験直前期は、短答対策ではなく、論文対策をメインに据える受験生が多いのではないかと思います。
このような予備試験の特性から考えると、予備試験においては、短答科目にある法律基本科目をまずは重点的に学習し、選択科目については短答後に突貫工事的に学習することでも仕方がない部分があると思います。
配点の観点からみても、選択科目は短答式試験がないことから、試験全体の配点としてみたときには、基本科目に比べて配点が低いともいえるので、その分学習のプライオリティを落とす戦略に合理性があるという見方もできます。
.
3.以上を踏まえた選択科目(経済法の付き合い方)
(1)司法試験の受験生の方
まず、司法試験対策においては、上述のように選択科目を軽視する合理性は全くありませんので、司法試験の受験生の皆様はしっかりと選択科目の対策をしていただきたいと考えています。 経済法に関して言えば、過去問対策が何よりも重要ですので、私が加藤ゼミナールのHP上で公開している経済法過去問のランクを確認いただき、少なくとも、Aランク、Bランクの問題(過去問の8割程度)までは取り組んでいただきたい(実際に問題を起案するかは別にして少なくとも、過去問で出題された論点を知らない状態にしないようにしていただきたい。)と考えています。
(2)予備試験の受験生の方
予備試験対策についても、過去問対策が重要であることは司法試験対策と同様です。
他方で、司法試験とは異なり、Aランクの問題に取り組んでいただければ対策としては十分ではないかと思います。また、Aランクについても分野別に問題を分類しているので仮にAランクすべての問題に取り組むのが時間的に厳しい方がいる場合には、各分野について数問ずつ取り組むようにしていただければ、大きな穴がなくなり、最低限の対策ができるのではないかと思います。