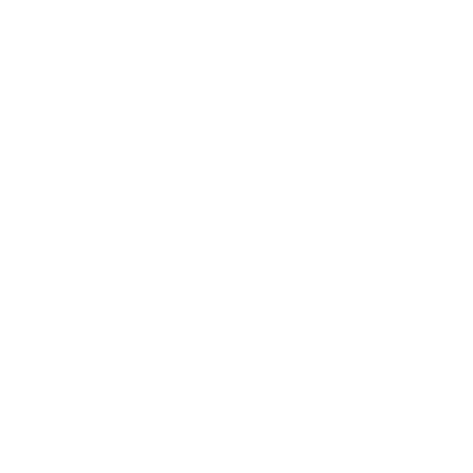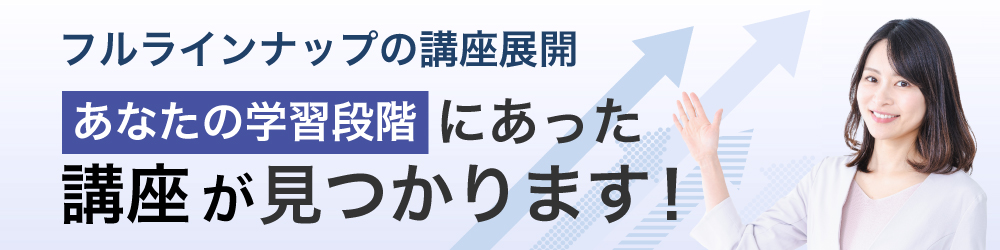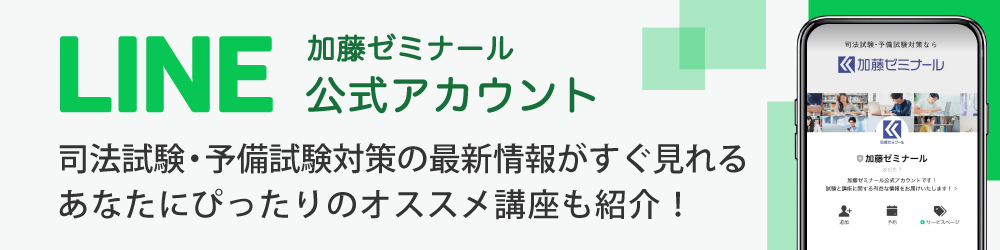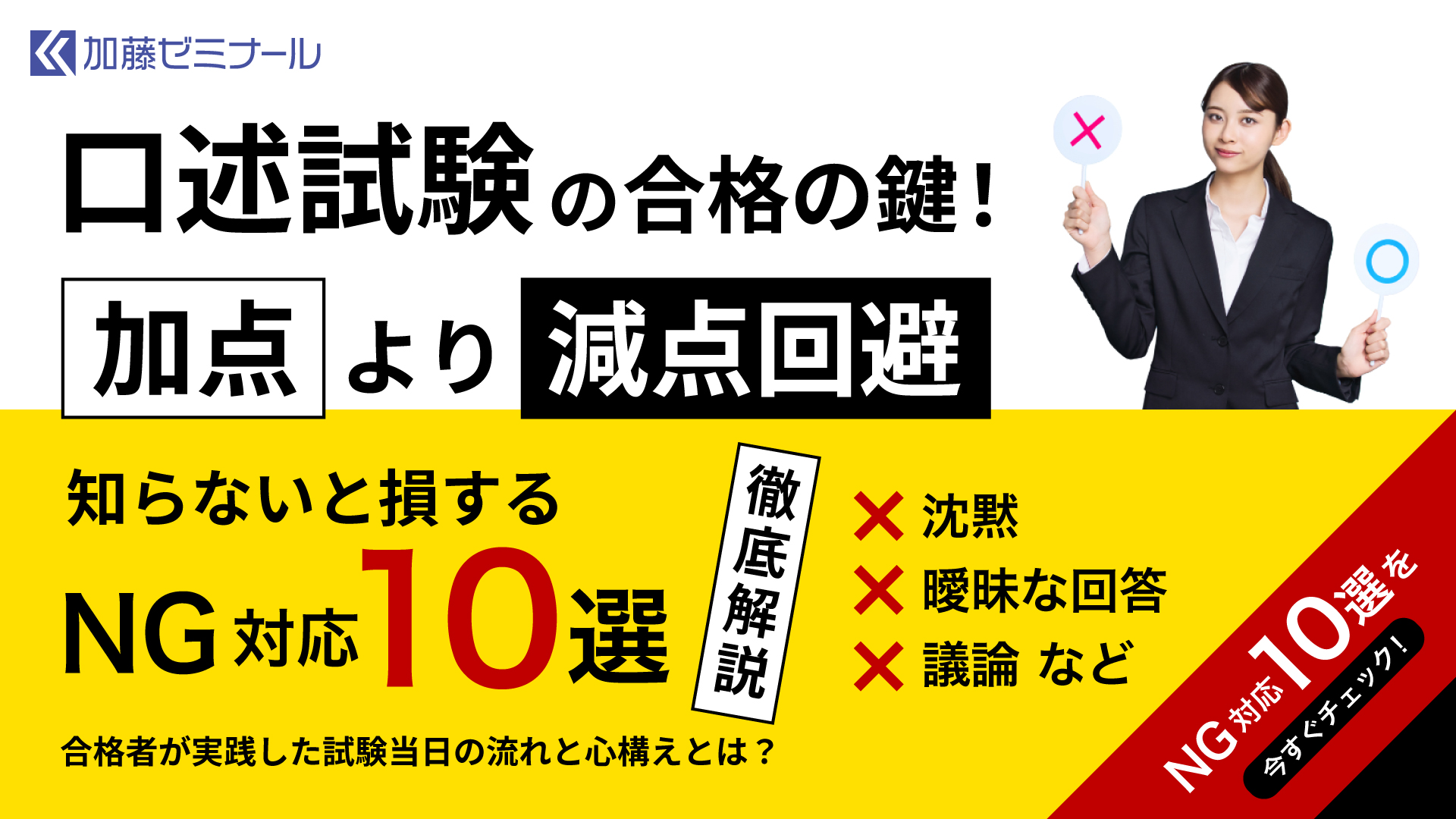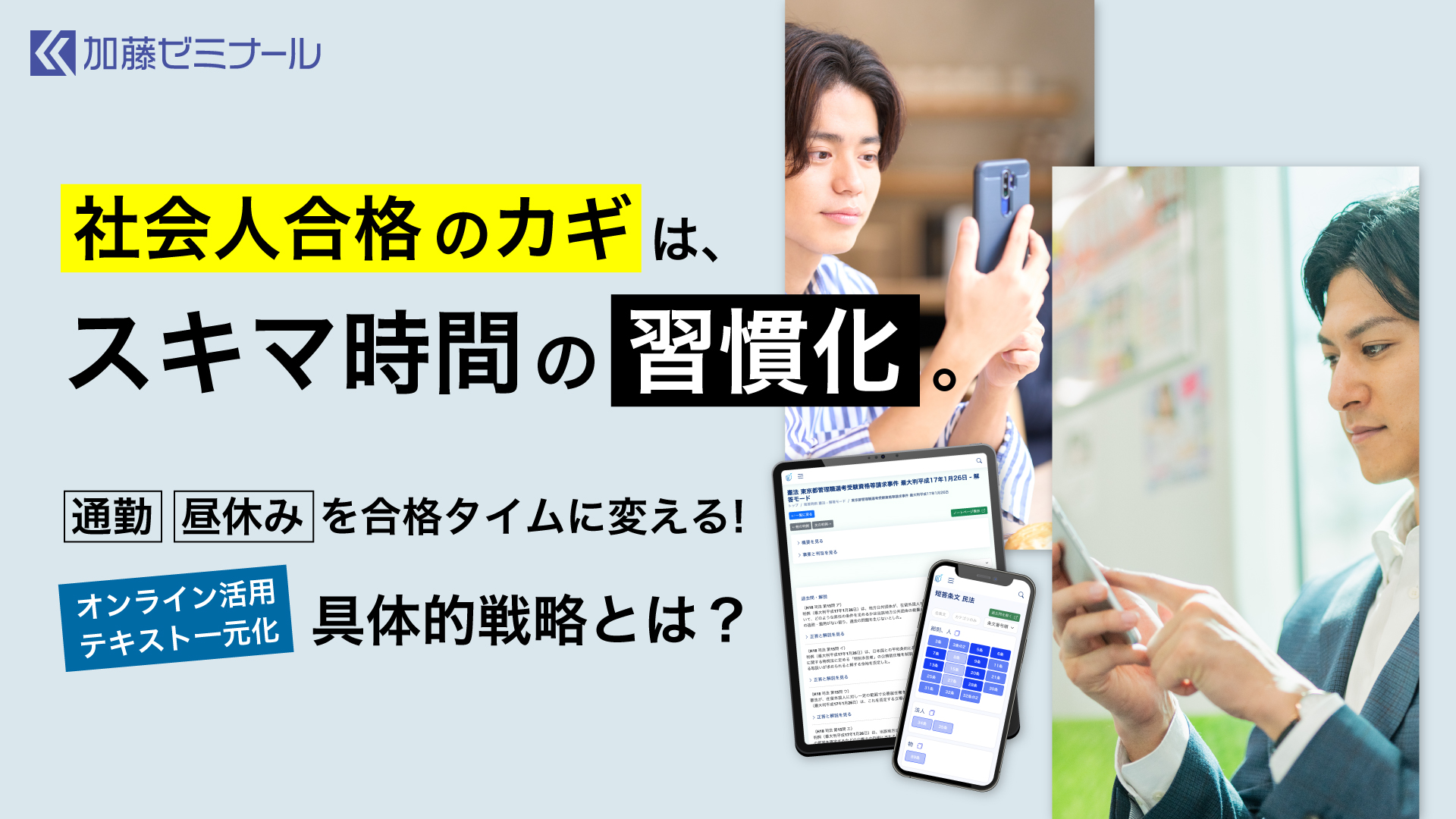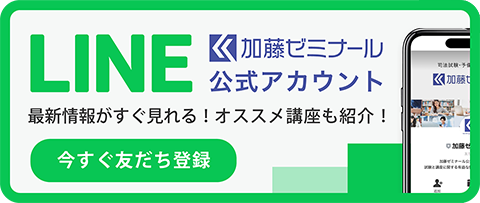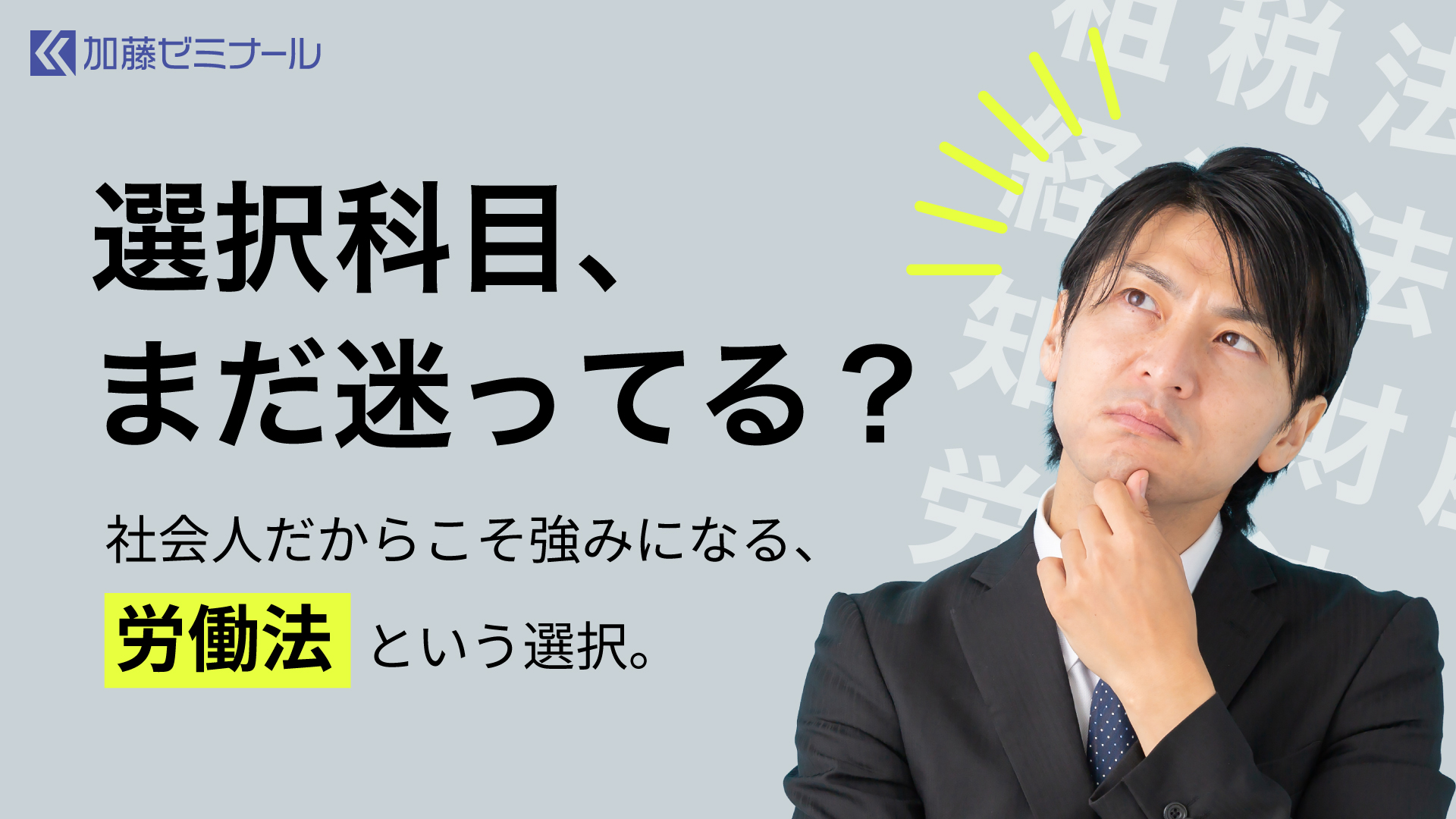
Contents
はじめに:選択科目の重要性と悩み
予備試験・司法試験において、一つの悩みとなるのが、選択科目です。
基本7科目と異なり、自分で科目を選べる自由がある一方で、「どの科目を選ぶべきか?」という悩みが生じます。
なかでも、会社で働きながら受験する社会人にとっては、時間や体力の制約もあり、なるべく効率よく、かつ自分の強みを活かせる科目を選ぶことが非常に重要になります。
そんな社会人受験生に、私がおすすめしたいのが「労働法」です。
本記事は、社会人の受験生の方が、選択科目を選ぶ際の一つの参考にしていただければと思います。
社会人受験生に労働法をすすめる理由
理由はシンプルです。
会社で働いているという経験そのものが、最大の強みになるからです。
労働法は、他の選択科目に比べて、会社で働いている社会人の実体験と密接に結びついています。
・採用や内定に関する経験
・就業規則を読んだことがある、その策定に関わったことがある
・残業や有給申請の経験
・労働組合に加入している
これらはすべて、労働法の試験で出題され得る重要なテーマです。
つまり、社会人ならばすでに学習の土台ができている可能性が高いのです。
社会人の経験が学習の武器になる
例えば、学生受験者の方が内定取消しに関する論点を初めて勉強する際、その背景事情や労働者・企業双方の立場をゼロから想像しなければなりません。
しかし、会社で働く社会人であれば、自分自身が内定を受けた経験や、採用面接に関わった経験があることも多く、また、内定時に契約書等を交わしていることが多いでしょうから、仕組みや用語、論点の理解が早くなります。
その他にも、以下のような項目は、社会人ならではの理解しやすさがあります。
・労働条件の明示義務 → 自分が入社した際に、採用過程で提示された労働条件と実際の労働条件が一致していたのかなどを踏まえて事案をイメージしやすい。
・残業代未払いや固定残業制 → 自分が残業をした際の経験から事案をイメージしやすい。
労働法で問題となる点は、会社員として働く社会人であれば実体験のみならず、ニュースや職場で経験したことが多く含まれるため、理解が非常にスムーズになります。
テキストや問題文が圧倒的に読みやすい
労働法で学習することになる論点、ひいては本試験の問題文は、まさに会社と労働者(=会社に勤める社会人)との間における労働紛争に関わることです。
これらの問題になる場面は、自分の会社内での具体的場面と置き換えてみながら普段の学習したり、問題文を酔うようにすると、イメージがしやすく、状況がすんなり頭に入り、学習や問題分析が進みやすくなります。
社会人受験生にとっては、学習時間が限られる中で、学習の最初にテキストや問題文を初見で一読した際に大体の意味が分かるということは大きなメリットになります。
また、本試験時において、問題文を読むスピードや事案把握のスピードが速いことも、それだけで大きな武器になります。
労働法は努力が結果に直結しやすい科目
労働法の特徴として、努力が素直に得点に結びつきやすいというメリットがあります。
これには次のような理由があります。
・条文化と判例によって、論点とその解が確立されているものが少なくない
・学んだ内容が現実とリンクしており記憶に残りやすい(特に社会人受験生)
実際に私自身も、社会人として働きながら学習したからこそ、労働法の学習はやった分だけ成果につながっているという感覚が早い段階からあり、学習初期の段階から理解の初速はかなり早かったと思います。
正しい学習を行って、判例等の考え方に沿って整理された答案作成ができれば、点数が安定しやすい科目であるといえます。
他方で、労働法はボリュームのある科目であるため、特に学習時間が限られる社会人受験生としては、メリハリを付けて、正しい知識を効率的に身に付けていくことが重要です。
私は、司法試験労働法1位の加藤喬先生(加藤ゼミナール代表・講師)の労働法講座を活用して労働法を学習しましたが、論点が網羅されているうえにメリハリをつけて整理されており、非常に効率的で効果的な学習をすることができました。
労働法を選択した方には非常におすすめできる予備校です!
社会人だからこそ書ける骨太の答案
社会人の受験生であれば、自分の労働者としての経験や管理職・人事担当などとしての視点を持っているため、答案作成時に必要な事実の拾い上げの精度が高くなったり、問題の所在を深く把握することができるため、答案に説得力と深みが出ると思います(採点者に理解・評価されやすい文章力につながるという趣旨)。
働いている現場感覚を活かして、具体的に事実を読み解き、拾い上げる。
これができるのも、社会人受験生の大きな強みです。
まとめ:自分の強みを活かせる選択を
社会人受験生の方に労働法がおすすめと述べてきましたが、結局は、興味や経験等からこれが良いと思えた科目を選択するのが最良だと思います。
選択科目をどれにするかは、司法試験の合否を左右し得る大きな選択の一つです。
もっとも、これまで述べてきた通り、社会人として働いているというだけで、労働法選択には大きなメリットがあると思います。
- 学習用のテキストや問題文を理解しやすい
- 実体験とリンクしており記憶しやすい
- 実生活がが学びに活きる+学習したことが今後の実生活でも活きる
- 事案の把握の精度が高く、答案も充実する
もし選択科目に迷っている社会人受験生の方がいたら、労働法を候補に入れてみてください。
受験において社会人であるという状況を不利と考えていたあなたの立場は、むしろ合格への武器になるかもしれません。
実務家弁護士T
社会人受験生として学習期間1年で予備試験に合格し、翌年の司法試験には、総合31位・オールAで一発合格