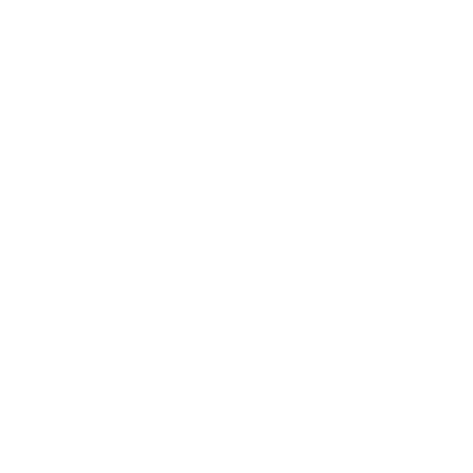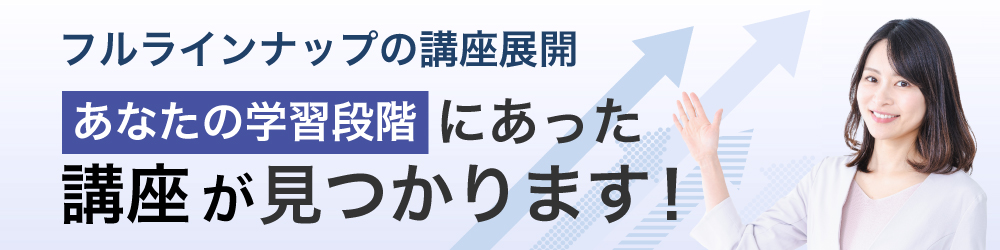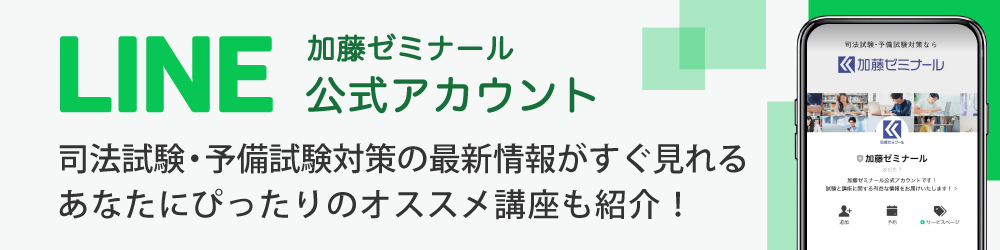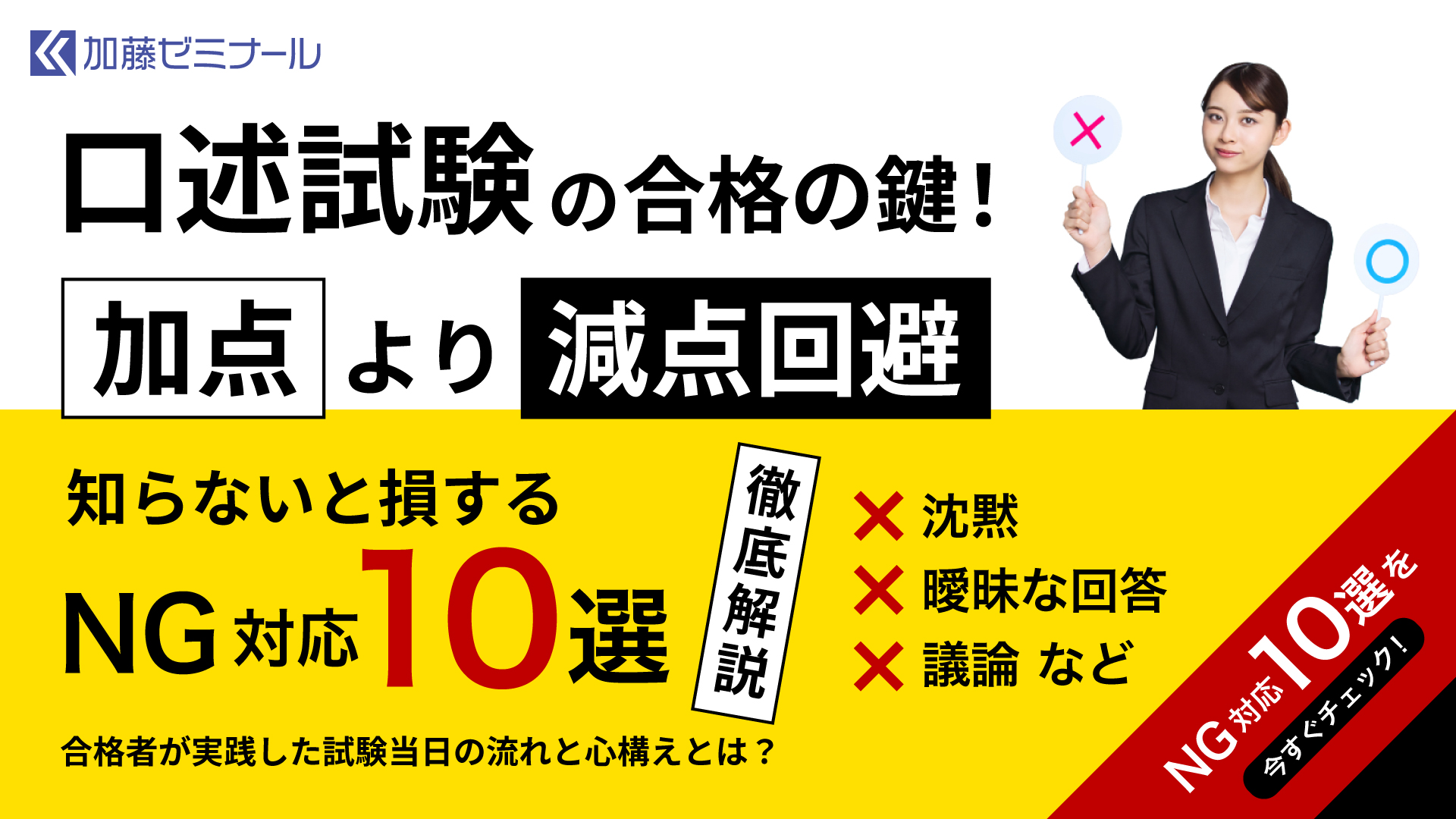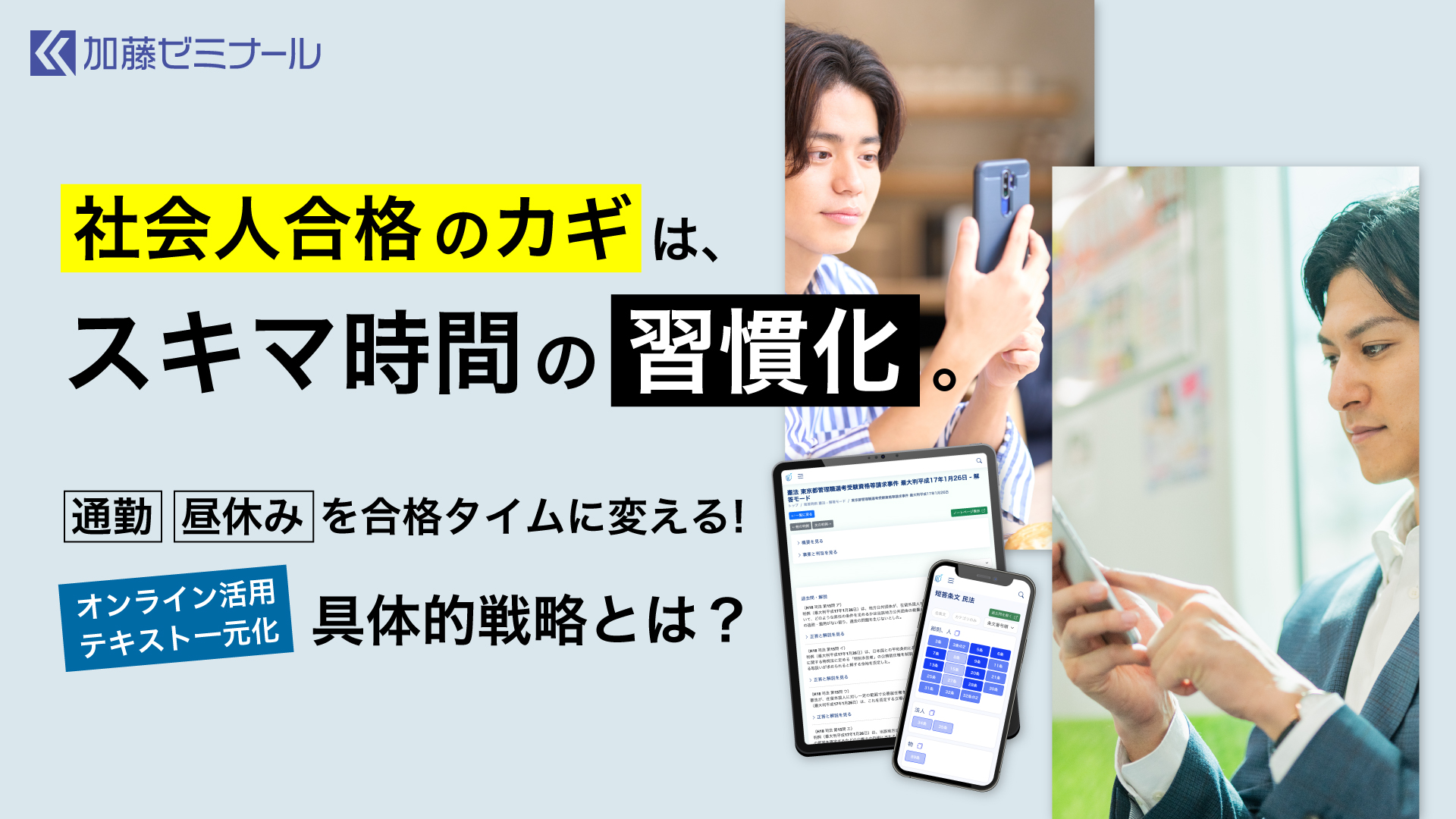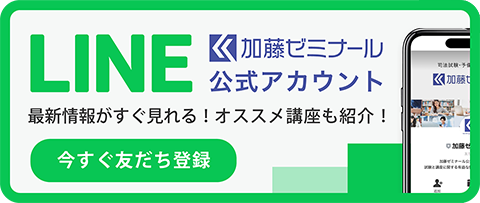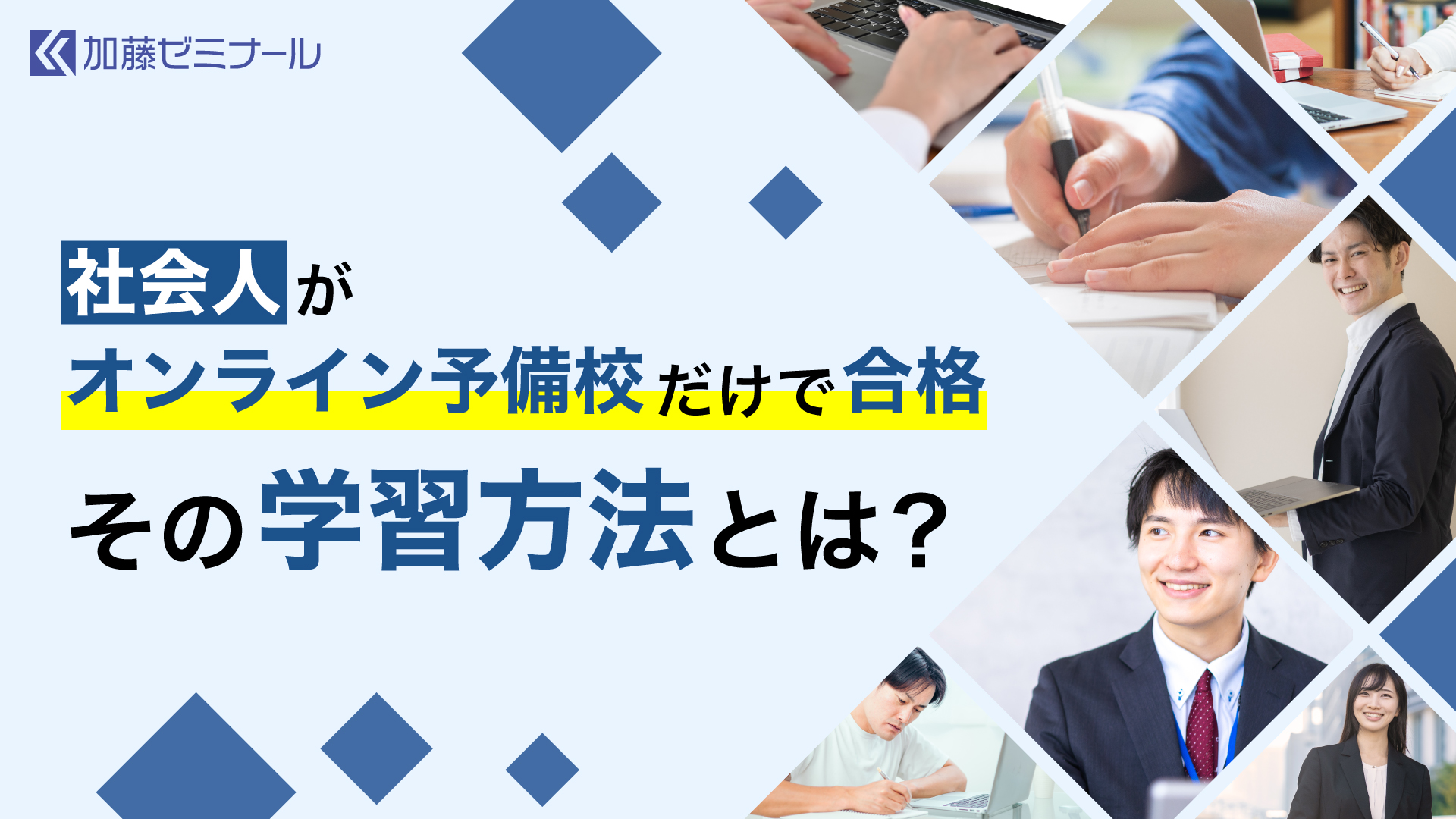
Contents
【予備試験・司法試験】基本書は必要?オンライン予備校だけで合格できる理由と活用法
はじめに
「予備試験に挑戦したいけれど、基本書を全部読む余裕なんてない」
「働きながら勉強していると、分厚い基本書を読む時間が取れない」
「オンライン予備校だけで本当に合格できるのか?」
こうした悩みは、初学者や社会人受験生に共通して生まれるものだと思います。かつての私自身も、同じように悩みました。ロースクールに進学せず、社会人として働きながら予備試験を突破するという目標を掲げていましたが、その学習方法を模索する中でたどり着いた答えは、「基本書は不要、オンライン予備校の活用だけで合格できる」というものです。
本記事では、私の実体験を交えながら、なぜ「基本書は不要で、オンライン予備校の活用だけで合格できるのか」について説明いたします。
さらに、どのように予備校を活用し、効率的に学習を進めるべきかについても具体的にお伝えします。
結論:基本書は不要。予備校活用だけで十分
先に結論を述べておきます。
正しいオンライン予備校を選び、徹底的に活用できれば、司法試験・予備試験合格に基本書は不要です!
合格に必要なのは、試験委員が重視するポイントを正確に押さえ、それを答案で表現できる力を養うことです。
分厚い基本書を隅から隅まで読んで学習することは、試験合格のためには不要であり、むしろ、非効率であり、限られた時間を浪費する結果になりかねません。
基本書と予備校テキストの本質的な違い
ここで、私が思う基本書と予備校テキストの違いを明確にしておこうと思います。
- 基本書
著者の学問的研究をベースに法律理論を詳しく取り上げる書籍であり、試験に直結する部分もある反面、試験で使わない少数説や試験範囲外の分野に関する記述も多い。
. - 予備校テキスト
合格という目的にコミットするために必要な知識とノウハウが集約されており、出題頻度や試験委員の評価基準を踏まえて情報が整理されている。
つまり、基本書は法律そのものを研究・学習するためのものであるのに対し、予備校テキストは予備試験・司法試験突破のために作られたものであるという、大きな目的の違いがあるのです。
予備校テキストが「合格」に直結する理由
私は司法試験対策で、加藤ゼミナールのテキストのみを使用しました。
その理由は、テキストが極めて高品質であり、特に以下の点で優れていると感じたからです。
- 出題可能性を踏まえて適切に濃淡を付けながら論点が網羅的に盛り込まれている
- 採点者である司法試験委員会側が答案で評価するポイントを明確に解説している
- 合格に必要な答案の書き方が、科目毎・論点毎に整理されている
一言でまとめると、合格に必要な知識と方法論がすでに一冊に凝縮されていると感じました。このような高品質の高い予備校教材を使えば、合格するために基本書を開く必要はありません!
基本書学習の落とし穴:周辺情報に時間を奪われる
基本書中心の学習をすると、次のような問題が起こります。
- 試験合格に直結しない学説の枝葉レベルのことに時間を取られる
- 試験の範囲や傾向を見誤る
- 情報量が多すぎて復習が追いつかないどころか、1周することもできない
特に社会人受験生にとっては、これは致命的です。時間がない受験生は、限られた時間でいかに効率の良い学習をするかが重要な命題です。
短期合格を目指すなら、試験に不要な情報を削ぎ落とす勇気が必要です。
基本書を「辞書的に使う」必要はあるのか?
「基本書を辞書的に使えばよい」との言説を目にすることがあります。しかし、私は、実際に予備校だけで勉強して予備試験に1年で合格し、司法試験に30番台で合格しているので、以下理由から、基本書を自署的に使うことも不要であると考えています。
- 正しい予備校を選べば、講義とテキストで十分に正確・詳細な知識を身に付けることができる
- 判例検索や予備校の問題集テキスト等の補助ツールでリサーチをすることも十分可能
つまり、予備校を活用する場合には、基本書を参照しなくても、予備校テキストで気になる箇所を調べるためのツールや環境が整っており、それだけで学習が完結するのです。
分からないときは講義に戻る!知識の一元化が最強の武器
学習を効率化する最大の秘訣は、テキストに知識を一元化することです。
そのためには、テキストの作成者と講師が一致していることが望ましいです。なぜなら、テキストの作成者と講師が異なると、論点の理解やノウハウなどに関する違いを通じて、講義内容とテキストの記述がずれることが少なくないため、インプットする側にも悪影響が生じ得るからです。
高い精度で講義と一体化されている予備校テキストであれば、テキストと講義に立ち戻ることで、理解の基盤を固めることができます。逆に、分からないたびに基本書を開くと、知識が散らばったり、普段使っている予備校テキストの内容に不安が生じるなどして、学習効率の低下にもつながります。
予備校を信じる決断と選び方のポイント
これまで、予備校テキストだけで足りると述べてきましたが、そのように一本化した学習を成功させるには、予備校を信じる決断が必要です。
予備校選びポイントは、以下の通りです。
- テキストが体系的に整理され、一元化されているか
- 講義とテキスト作成を同じ講師が担当しているか
- 講義が丁寧で分かりやすく、初学者でも理解できるか
- 受講相談や問い合わせで、教材の完結性を確認できるか
不安であれば、実際に講義を試聴し、この内容であれば合格まで走り抜けられると確信を持てるかどうかを実際に確認しましょう。
実体験:私は基本書ゼロで予備試験・司法試験を突破した
私自身、司法試験合格まで一度も基本書を開きませんでした。
学習の中心は、オンライン予備校のテキストと講義だけ(一部、アプリや六法等も使用)。
その結果、予備試験も司法試験もそれぞれ1年で突破できたのです。
この実体験からも基本書を読まなくても合格は十分可能だと思っています。むしろ、社会人で時間のない中で、効率を重視すればするほど、予備校一本化が正解だと言えると改めて感じています。
まとめ:予備校一本化で合格は十分可能
これまでに述べてきた通り、予備試験・司法試験の合格に基本書は不要であると言えます。
- 予備校テキストには「合格に直結する知識と方法論」が凝縮されている
- 基本書は学問的で、周辺情報が多く非効率になりやすい
- 知識を一元化し、講義とテキストを信じて走り抜けることが重要
適切なオンライン予備校を選び、教材を徹底的に活用することこそ初学者が最短で合格する道です。
「不安にならずに予備校に依存する」
この決断こそが、合格への最短ルートを切り開きます。
実務家弁護士T
社会人受験生として学習期間1年で予備試験に合格し、翌年の司法試験には、総合31位・オールAで一発合格