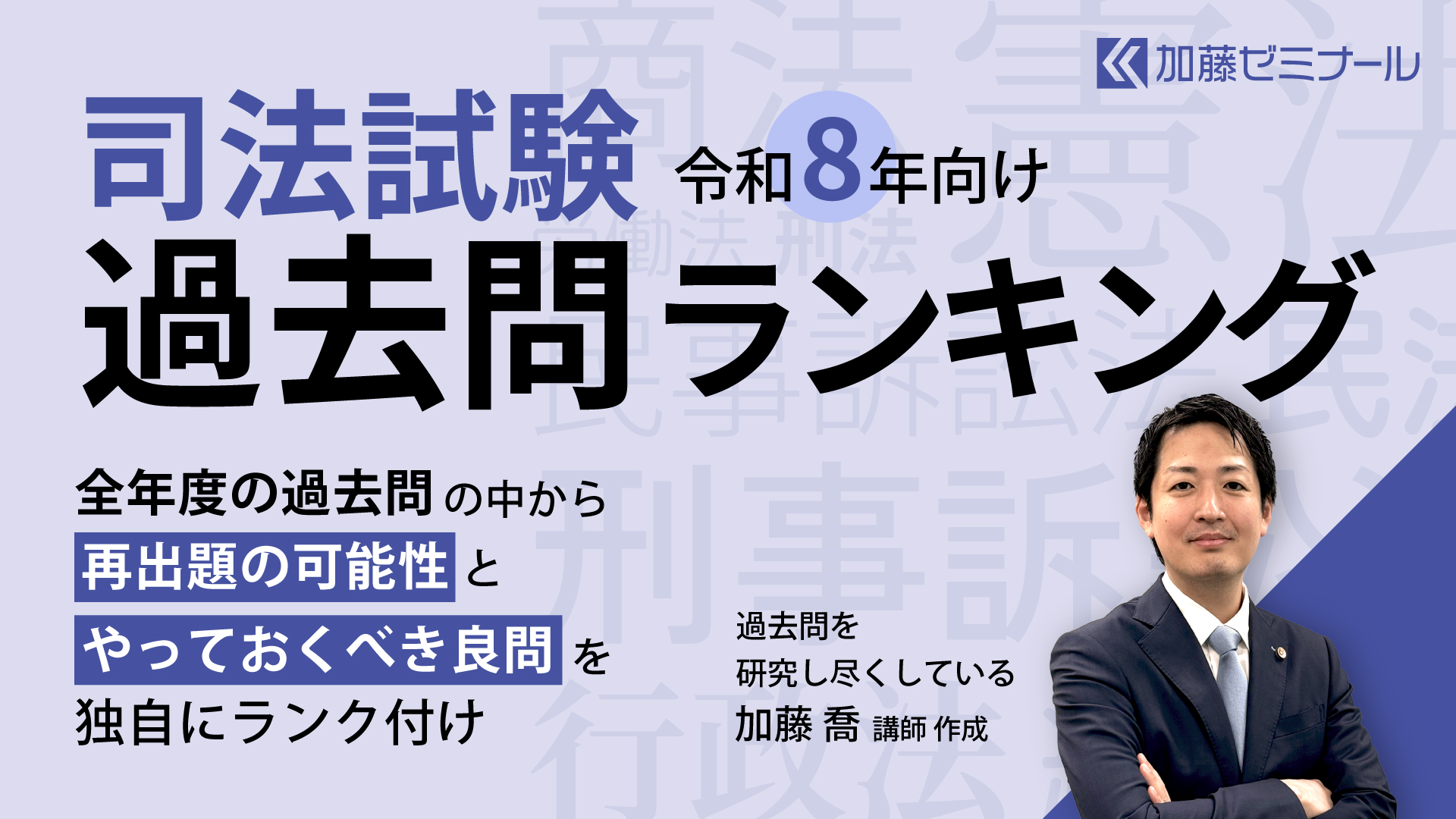
司法試験過去問ランキングを令和8年司法試験向けに更新しました。
ランク付けは、基本7科目及び労働法は加藤喬講師が、経済法は加藤駿征講師(総合5位・経済法1位の実務家弁護士)が、倒産法は深澤直人講師(総合200番台合格、ロースクール主席卒業)が作成しています。
過去問をやる意味は主として、①出題傾向の把握、②再度の出題に備える、③受験技術の習得にありますが、下記のランクは①~③を総合考慮して作成したものです。
憲 法
憲法では、分野・論点単位での再度の出題可能性に備えることよりも、違憲審査の基本的な枠組み(保障→制約→違憲審査基準の定立→目的手段審査による当てはめ)が妥当する問題における答案の書き方(=違憲審査の基本的な枠組みを正しく使いこなす力)を身に付けることが重要であり、そのために特に有益なのが平成30年~令和2年の3問です。
また、憲法では、人権選択から目的手段審査による当てはめに至るまで、何についてどう論じるべきかについて問題文のヒントで誘導される傾向が強いので、こうした誘導に従って何をどう論じるべきかを判断できる ” 問題文の読み方 ” を身に付けることも非常に重要です。こうした ” 問題文 ” の読み方を身に付ける上でも平成30年~令和2年の3問は大変有益です。
なお、平等権、財産権、生存権など違憲審査の基本的な枠組みが妥当しない分野については、出題可能性も踏まえながら過去問や短文事例問題(基礎問題演習講座など)で確認しておきましょう。
| Aランク | H18 H19 H23 H30 R1 R2 R5 |
|---|---|
| Bランク | H20 H21 H24 H25 H26 H28 H29 R3 R6 R7 |
| Cランク | プレ H22 H27 R4 |
行政法
行政法では、刑事訴訟法と同様、出題分野が狭い分、過去問から再度出題される可能性が高いので、ランク付けによる重要度に応じて濃淡をつけながらなるべく全問やるべきです。
例えば、令和7年司法試験で出題された病院開設中止勧告の処分性を認めた平成17年最判の判例理論(H20 R5 R7)、差止訴訟における「重大な損害」(プレ H23 H27)は過去問で複数回出題されています。
また、行政裁量(H22 H23 H24 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R3 R4 R5,R7)、処分性(プレ H19 H20 H24 H25 H29 R2 R3 R5 R6,R7)及び原告適格(H21 H23 H26 H28 H29 H30 R4 R5)は司法試験の三大頻出分野であり、過去問を通じて講学上の判断枠組みを使いこなせるようになるとともに、判例理論や出題パターンの処理手順も習得しておく必要があります。
行政法は、刑事訴訟法の次に、過去問からの出題可能性が高い科目であるといえます。
なお、出題の頻度からして、令和8年司法試験では原告適格(そのうち、法律上保護された利益説を用いるもの)が出題される可能性が極めて高いので、しっかりと対策をしておきましょう。
| Aランク | H24 H26 H27 H29 H30 R1 R5 |
|---|---|
| Bランク | プレ H18 H19 H20 H21 H25 R2 R4 R6 R7 |
| Cランク | H22 H23 H28 R3 |
民 法
民法では、出題範囲が広い分、過去問から出題される可能性はさほど高くありませんので、再度の出題可能性に備えることに重点を置くべきではありません。
民法では、論点よりも、法律要件を事実と条文の番号・文言を結び付けながら1つひとつ認定する過程が重視されることが多いです。債権者代位権、詐害行為取消権、契約不適合責任、不当利得、不法行為責任、相続による権利承継などでは、特にそうです。こうした出題では、文章力、条文操作を含め真の実力が問われますから、要件認定の作法を身に付けることを意識しましょう。
また、例えば「Aは、錯誤による意思表示の取消し(95条1項)により甲土地の売買契約が遡及的に無効になる(121条)と主張して、これにより発生する原状回復請求権(121条の2第1項)を行使して代金1000万円の返還を請求する。」というように、答案冒頭における訴訟物と主張の骨子の指摘でも差が付きます。
このように、民法では、分野・論点単位での再度の出題可能性に備えることよりも、要件認定の作法や答案冒頭における書き出しといった ” 答案の書き方 ” を身に付けることに重点を置く必要があります。
| Aランク | H23 H27 H28 H29 R2 R5 |
|---|---|
| Bランク | H18 H20 H24 H25 R4 R6 R7 |
| Cランク | プレ H19 H21 H22 H26 H30 R1 R3 |
商 法
商法では、過去問から出題される可能性がそれなりに高い一方で、特殊な解法や書き方の習得は不要なので、主として再度の出題可能性に備えるために過去問をやることになります。
1問当たりの分析はさほど重くないことも踏まえると、刑法と同様、重要度に応じて濃淡をつけながらなるべく網羅的にやるべきです。
なお、会社法論文の肝は条文です。論点偏重の学習ではなく、ちゃんと条文学習もやりましょう。日頃から条文の検索・操作に慣れておくことも重要です。
それから、組織再編の効力発生前後における争い方(司H21 予H25 予28)と詐害的会社分割における残存債権者の救済手段(出題実績なし)はいつ出題されてもおかしくないので、会社法上の手段を網羅的に論じることができるように準備しておきましょう。
| Aランク | H20 H21 H22 H23 H26 H27 H29 R3 R5 R6 |
|---|---|
| Bランク | H19 H24 H25 H28 H30 R2 R7 |
| Cランク | プレ H18 R1 R4 |
民事訴訟法
民事訴訟法では、特殊な答案の書き方が求められる分野・論点は少ないので、主として、再度の出題可能性に備えることと、捻り効いた問題に対応する力を身に付けるために過去問をやることになります。
訴えの主観的追加的併合を否定する判例の射程は頻出であり(H20 H28 H30 R4)、判例の理由付けを深く理解しておく必要があるので、H30とR4の過去問で必ず確認しておきましょう。
近年は管轄(R1)や違法収集証拠(R5)などのマイナー分野からも出題されているので、送達や再審あたりから出題される可能性もあります。
| Aランク | H23 H24 H27 H29 H30 R3 R6 |
|---|---|
| Bランク | H21 H25 H28 R1 R2 R4 R5 |
| Cランク | プレ H18 H19 H20 H22 H26 R7 |
刑 法
刑法では、主として、再度の出題可能性に備えるために過去問をやることになります。また、刑法全般に共通する答案の書き方を身に付けることも大事です。
特殊な解法や書き方が要求されない分、1問当たりの分析はさほど重くないことも踏まえると、重要度に応じて濃淡をつけながらなるべく網羅的にやりましょう。Aランク以外はフル起案する必要はなく、Bランクは答案構成だけ、Cランクは答案例を解答筋と論点をざっと確認するだけでも良いです。
なお、司法試験では正当防衛・誤想防衛の出題頻度が非常に高く(H18 H23 H27 H29 R1 R4 R6)、近年の出題内容からすると、令和8年又は令和9年には令和3年や令和6年のように正当防衛で現場思考論点が出題されたり重要論点について深い考察が求められる可能性があります。
| Aランク | H20 H21 H23 H24 H25 H27 H28 R1 R2 R3 R6 |
|---|---|
| Bランク | プレ H18 H22 H26 H29 R4 R5 |
| Cランク | H19 H30 R7 |
刑事訴訟法
刑事訴訟法では、行政法と同様、出題分野が狭い分、過去問から再度出題される可能性が高いので、ランク付けによる重要度に応じて濃淡をつけながらなるべく全問やるべきです。
例えば、令和5年はH22(領置)とH21・H25(実況見分調書)の類題であり、令和6年も違法性承継論等を除けばH18(所持品検査)とH30(ビデオカメラでの撮影)の類題です。
また、令和7年司法法試験では、逮捕に伴う無令状捜索(H18 H24 H25)、被疑者を移動させた上での無令状捜索(H25)、弾劾証拠における限定説(H29)はいずれも過去問で出題されており、公判前整理手続終了後における新たな証拠調べ請求(316条の32第1項)については、それ自体としては初の出題ですが(※予備試験の刑事実務基礎科目では出題実績あり)、公判前整理手続終了の効果という問題意識は、過去に2度出題されています(H28:公判前整理手続終了後における被告人側の新たな主張・供述等、R1:公判前整理手続終了後における訴因変更請求)。
このように、刑事訴訟法は、過去問からの出題可能性が一番高い科目です。過去問で1回でも出題されている論点については、いつ出題されてもおかしくありませんから、「今年は出題されないだろう」などと考えずに、ヤマを張ることなく、満遍なく勉強しておきましょう。この意味において、刑事訴訟法における過去問のランク付けは、やるべき過去問とやらなくていい過去問を棲み分けるという取捨選択の基準ではなく、全過去問をやる際の濃淡付けの基準にとどまります。
| Aランク | プレ H21 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 |
|---|---|
| Bランク | H20 R2 R3 R4 R5 R6 |
| Cランク | H18 H19 H22 R1 R7 |
労働法
労働法の司法試験過去問は令和7年までで40問(20年分×2)もあり、労働法の合格答案の水準や出題範囲の広さなども踏まえると、過去問を全問隈なくつぶすという方法は得策ではありません。仮に全問やるとしても、Aランク以外については、ざっと問題文と解答に目を通して事例と条文・論点の対応関係や答案全体の流れを確認するにとどめるべきです。
労働法重要問題100選講座では、A・Bランク論点をほぼ網羅している上に司法試験過去問の重要部分も取り上げているので、本講座の受講者様なら尚更、司法試験過去問を全問隈なくやる必要はありません。
労働法は、出題範囲が広く過去問以外からも出題されるうえに、解法や書き方に特徴があるわけでもないので、インプット重視の勉強が奏功する科目であるいえます。私自身、受験生時代に労働法の過去問をフル起案したことはほとんどなく、過去問については、出題趣旨・採点実感だけに目を通して出題傾向や重要分野論点のポイントを確認しただけでした。
第1問
| Aランク | H25① H26① H27① H29① R4① R7予備 |
|---|---|
| Bランク | H19① H21① H22① H24① H30① R1① R3① R5予備 |
| Cランク | H18① H20① H23① H28① R2① R4予備 R5① R6① R7① |
令和6年司法試験第1問では懲戒解雇を理由とする退職金支給制限が出題され、令和7年司法試験第1問では退職後の競業避止義務違反を退職金支給制限が出題されているため、令和8年司法試験との関係では退職金支給制限に関する問題(H18①、R1①)の重要度は下がります。
定額残業代制は重要論点であり、司法試験では過去に2度出題されていますが(H21①、R2①)、いずれも新しい要件である対価性要件は問われない問題でした。令和7年予備試験では、定額残業代制における対価性要件が正面から問われていることから、次回、司法試験で定額残業代制が出題されるとしたら、対価性要件を正面から訊いてくるはずです。こうしたことを踏まえて、定額残業代制における対価性要件を問わない平成21年司法試験第1問・令和2年司法試験第1問のランクをB~Cランクとする一方で、定額残業代制における対価性要件を正面から問う令和7年予備試験をAランクに位置付けています。
出題の頻度・傾向からして、令和8年司法試験では、過去問で出題された論点としては、就業規則の不利益変更(特にH23②、H29①)、整理解雇(H22①、R③①)、配転命令(H21①、H26①、R4①)、試用期間(平成25①)の出題可能性が高いです。また、未出題論点としては、労働基準法上の労働者概念、採用内定、在籍出向の有効性はいつ出題されてもおかしくありません。
第2問
| Aランク | H23② H24② H27② H30② R3② R6予備 |
|---|---|
| Bランク | H21② H25② H26② H29② R2② R4② R5② R7② |
| Cランク | H18② H19② H20② H22② H28② R1② R6② |
令和7年司法試験第2問では、ストライキの正当性が出題されているため、ストライキの正当性に関する問題は重要度をB~Cに下げています。また、使用者側の言論の自由、支配介入行為の使用者への帰責も出題されているため、これらに関する問題もB~Cランクに下げています。さらに、ユニオン・ショップ協定、チェック・オフは、本来は重要度の高い分野ですが、令和6年司法試験第2問で出題されているため、令和8年司法試験における重要度は下がります。
他方で、出題の頻度・傾向からして、労働協約による労働条件の不利益変更、労働協約の一般的拘束力、組合活動を理由とする不利益取扱い、団体交渉拒否の不当労働行為の出題可能性が高いといえるので、これらに関する問題のうち特に重要と考えるもの(H23②、H24②、H27②、H30②、R3②)をAランクに位置付けています。また、支配介入は超頻出であり、ヤマを張るほどの分野ではないため、ランク付けをする際には考慮していません。
経済法
経済法のランク付けは、加藤ゼミナールで経済法講座を担当している加藤駿征弁護士(経済法1位・総合5位で司法試験合格、実務家弁護士)が作成しております。
| Aランク 23問 |
【ハードコアカルテル】5問 |
|---|---|
| Bランク 16問 |
【ハードコアカルテル】6問 |
| Cランク 5問 |
【非ハードコアカルテル】1問 |
倒産法
倒産法のランク付けは、加藤ゼミナールで倒産法講座を担当している深澤直人講師が作成しております。
なお、司法試験では「第1問:破産法、第2問:民事再生法」という出題が多いですが、平成18年~平成20年は「第1問:破産法、第2問:破産法」 平成21年・平成25年は「第1問:民事再生法、第2問:破産法」という出題になっています。
第1問
| Aランク | H25① H26① H29① R2① R3① R7予備 |
|---|---|
| Bランク | H20① H24① R4予備 R5① R6① R7① |
| Cランク | H18① H19① H21① H22① H23① H27① H28① H30① R1① R4① R6予備 |
第2問
| Aランク | H22② H25② H28② H30② R1② R2② R5② R5予備 R6② |
|---|---|
| Bランク | H18② H26② H29② R7② |
| Cランク | H19② H20② H21② H23② H24② H27② R3② R4② |