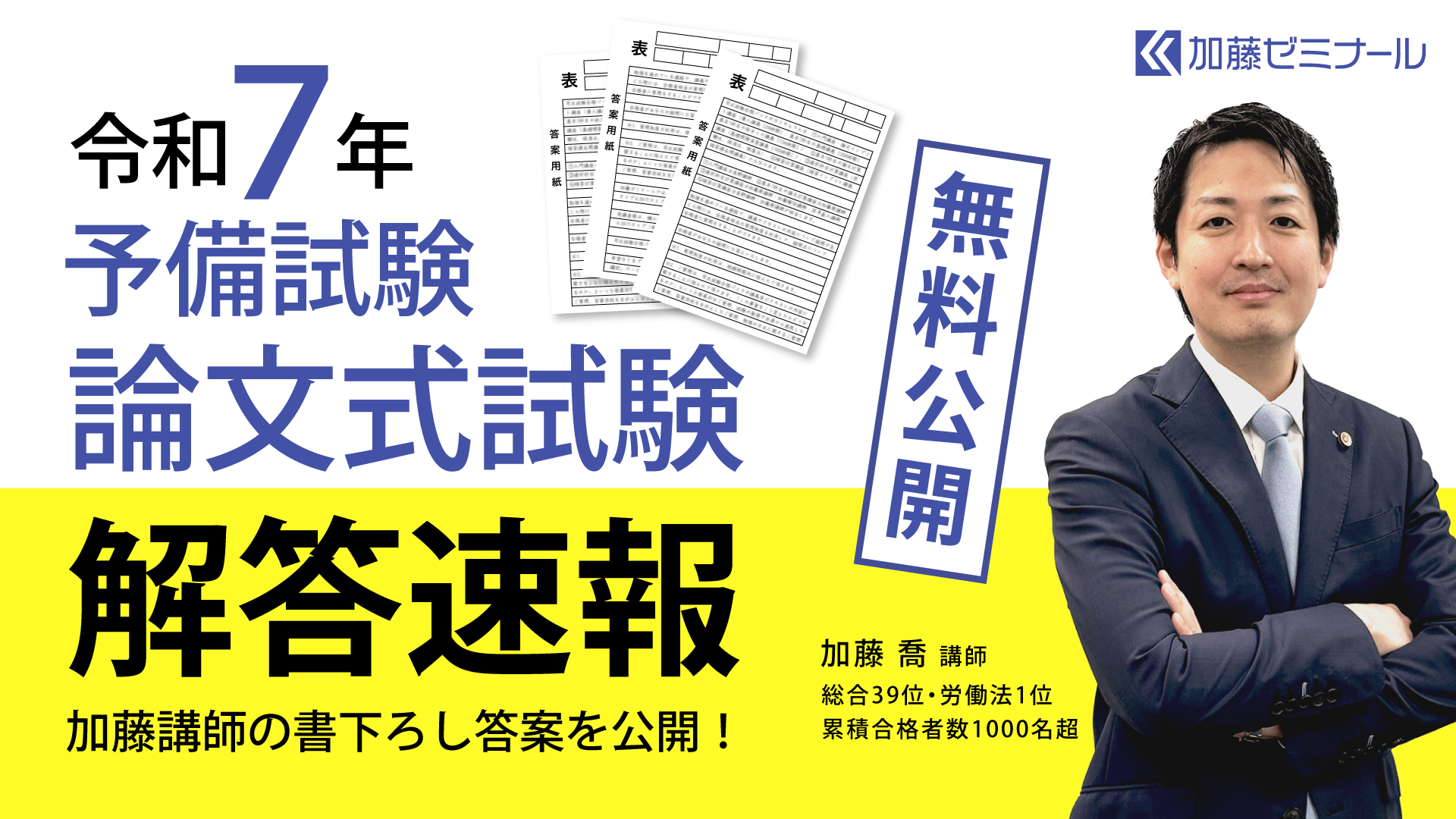
令和7年予備試験論文式の解答速報ページとなります。
基本7科目と選択科目(労働法・経済法・倒産法)の参考答案と解説を公開しております。
基本7科目と労働法は労働法1位・総合39位の加藤喬講師、経済法は経済法1位・総合5位の加藤駿征講師(実務家弁護士)、倒産法は深澤直人講師(実務家弁護士)が担当しています。
試験傾向を分析したり、ご自身の答案を評価する際に、お役立ていただけたらと思います。
憲 法
青少年の健全育成という立法目的に基づく有害差別図書の販売等の規制を定める法律(以下「新法」という。)の憲法21条1項適合性が問われており、類題としては、フィルタリングソフト法案の憲法21条1項適合性が問われた平成20年司法試験「憲法」、有害図書の販売等の規制を定める自主条例案の憲法21条1項適合性が問われた平成30年司法試験「憲法」が挙げられ、参考判例としては岐阜県青少年保護育成条例事件(最三小判例 平成元年9月19日)が挙げられます。なお、基礎問題演習講座「憲法」第20問でも同種の問題を取り上げています。
設問では、「参考とすべき判例に言及し」とあるため、岐阜県青少年保護育成条例事件をはじめとする参考判例に明示的に言及しながら論じる必要があり、その際には、同事件に付されている伊藤正己裁判官の補足意見にまで言及することが重要になってきます。なお、目的手段審査(当てはめ)では、参考判例に言及すれば、その分だけ紙面を食うことになるとともに、着眼点が絞られてしまうため、問題文の事情を使い切ることができないという悩みもありますが、私の答案では、問題文の事情を使い切ることよりも、参考判例に言及することを優先しています。この種の問題において、「参考となるべき判例に言及し」という指示に反して問題文の事情を網羅的に取り上げると、観点を羅列したにとどまる答案になってしまう可能性もあるからです。
問題文の最後には、「新法施行と同時に図書Aが包括指定を受け、その後、図書Bが個別指定を受けた。」とあり、設問(1)では「青少年が図書Aを購入できないこと」の憲法21条1項適合性が、設問(2)では「成人が年齢確認を受けなければ図書Bを購入できないこと」の憲法21条1項適合性が問われています。
問題文の最後に引っ張られて、設問(1)では包括指定自体の憲法21条1項適合性を、設問(2)では個別指定自体の憲法21条1項適合性を検討するのでは?と考える人もいるかもしれませんが、それは違います。本問で検討するべきは、適用違憲(処分違憲)ではなく、新法自体の法令違憲です。問題文には、図書Aに対する包括指定及び図書Bに対する個別指定について、適用違憲(処分違憲)を論じることができるだけの個別の事情が書かれていないからです。
したがって、設問(1)では、青少年の閲読の自由との関係で、新法のうち包括指定を定める部分の憲法21条1項適合性を論じ、設問(2)では、成人の知る自由との関係で、新法のうち個別指定を定める部分の憲法21条1項適合性を論じることになります。
なお、本問では、規制対象がヘイトスピーチを内容とする有害差別図書であるという特集性があり、憲法21条1項適合性を論じる際には、ヘイトスピーチというテーマについても論じる必要があります。その際には、ヘイトスピーチ自体の規制ではなく、ヘイトスピーチを内容とする有害差別図書を閲読する自由の規制の憲法21条1項適合性が問われているという問題状況を踏まえて、ヘイトスピーチという問題点を違憲審査のどこで・どう論じるのかについて、工夫をする必要があります。私の答案では、ヘイトスピーチという点は、目的手段審査(当てはめ)で言及するにとどめ、ヘイトスピーチであることを理由に知る自由の保障が否定されるのではないか、違憲審査基準が緩やかになる(中間審査の基準よりも緩やかになり、合理的関連性の基準にまで下がる)のではないか、という点については、敢えて言及していません。本問において、ヘイトスピーチという点は、岐阜県青少年保護育成条例事件における有害図書の内容との違いを通じて、主として目的手段審査で取り上げるべきテーマに位置付けられていると考えます。
<理想解>
<現実解>
憲法の現実解では、理想解に比べて、判例に関する言及をシンプルにしています。
法廷意見については、「判例は、…」という書き出しにしていますが、よど号ハイジャック記事抹消事件については事件名には言及していません。設問で「参考とすべき判例に言及し」という指示がある以上、「判例は、」「○○事件判決は、」という形で、判例に関する記述であることを明示するのが理想的ですが、事件名に言及することは合格水準としては必須ではないと考えています。また、補足意見については、事件名や補足意見であることの明示はしておらず、参考にした論述をするにとどめています。
理論面が薄く、シンプルである分、当てはめで点数を稼ぐ必要があります。そこで、問題文の事実をなるべく網羅的に拾い、具体的に評価するようにしています。
行政法
設問1
設問1では、転飼許可の取消訴訟における既存の許可業者の原告適格が問われています。既存の許可業者の原告適格は、一般廃棄物収集運搬業の許可との関係で、令和5年予備試験でも出題されています。
解答におけるポイントは、次の2つです。
設問2
設問2では、転飼許可の適法性が問われています。
条例3条2項1号の不許可事由に関する判断について都道府県知事の要件裁量を認めた上で、判断過程審査をすることになりますが、ここでポイントになるのが、【蜜源に対して蜂群数が「著しく」過剰である場合に限って条例3条2項1号の不許可事由に当たるとして許可をしない方針】に従って判断をすることの可否です。
最三小平成27年3月3日は、「行政手続法…12条1項に基づいて定められ公にされている処分基準」について、「裁量権の行使における公正かつ平等な取扱いの要請や基準の内容に係る相手方の信頼の保護等の観点」を根拠に、「当該処分基準の定めと異なる取扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り、そのような取扱いは裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たることとなるものと解され、この意味において、…行政庁の…裁量権は当該処分基準に従って行使されるべきことがき束されて」いるとして、法的拘束力を認めています。しかし、上記方針は、裁量基準として定められたものではありませんから、最三小平成27年3月3日のように考えて、法的拘束力を認めることはできません。せいぜい、「一定条件の下で、上記方針に従って裁量権を行使することができる」にとどまります。
全体
設問1における既存の許可業者の原告適格は令和5年予備試験で出題されていますし、設問2は応用要素のある問題ですが、応用の土台となる判例知識は平成28年予備試験で出題されていますから、予備試験過去問をちゃんとやっていれば解答できる問題であり、過去問との相性が良い出題であったといえます。
<理想解>
<現実解>
当てはめ重視の答案にしており、設問1においては、許可業者の営業上の利益に関する参考判例や学説について明示的に言及することはできていません。合格者も含めて受験生の大多数は、理想解のような論述をすることができないからです。
手引と運用については、ここまで分かりやすく問題文で誘導されているため、無視することはできません。もっとも、ここで悩んで時間を使うのは得策ではありませんから、設問1ではおまけとして最後に言及するにとどめており、設問2でも、運用の位置付けに関する抽象論は最低限にとどめており、平成27年最判の射程には言及していません。
民 法
設問1
小問(1)では、債務者所有不動産と物上保証人所有不動産に第1順位の共同抵当権が設定されており、物上保証人所有不動産から先に競売する異時配当がなされた場合において、物上保証人が債務者所有不動産の第1順位の抵当権を代位行使するための法的根拠が問われています。
民法392条は全ての抵当不動産が債務者所有不動産である場合にのみ適用される規定であるため、上記の場合には、392条ではなく、弁済者代位に関する規定(499条以下)が適用されます。したがって、物上保証人Cは、弁済者代位(499条、500条)として、甲土地の第1順位の抵当権を実行することができます。
道垣内弘人「担保物権法」第4版212頁でも「後順位抵当権者のことを規定している民法392条2項では不可能であり、民法500条・501条〔改正案499条・500条〕に根拠を求め、代位の法理によることになる。そして、後順位抵当権者が存在しないとき代位の法理で処理する以上、後順位抵当権者が存在する場合も同様に解すべきである。」としており、判例(最一小判昭和44年7月3日)も同様の立場です。
なお、Cは、物上保証人として「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たるため、原債権の移転について債権譲渡の対抗要件(467条)を具備する必要はありません(500条括弧書)。
小問(2)では、物上保証人が債務者所有不動産の第1順位の抵当権を代位行使する権利と物上保証人所有不動産の後順位抵当権者の権利の優劣が問われています。
判例(最三小判昭和53年7月4日)は、「民法392条2項後段が後順位抵当権者の保護を図っている趣旨にかんがみ、物上保証人に移転した一番抵当権は後順位抵当権者の被担保債権を担保するものとなり、後順位抵当権者は、あたかも、右一番抵当権の上に民法372条、304条1項本文の規定により物上代位をするのと同様に、その順位に従い、物上保証人の取得した一番抵当権から優先して弁済を受けることができるものと解すべきであるからである」として、後順位抵当権者の権利を優先する見解を採用しています。
この見解によると、各人の配当額は、D:3600万円、C:1200万円、H:0円、となります。
設問2
小問(1)は、適法な承諾転貸の事案において原賃貸人(所有者)が転借人に対して賃借物の返還を求めるための理論構成を複数検討させる問題です。
検討するべき請求は、①Gが、Hに対し、所有権(民法206条)に基づく返還請求権を訴訟物として、丙土地の明渡しを請求することと、②Gが、Hに対し、613条1項に基づき、原賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権を訴訟物として、丙土地の明渡しを請求することの2つです(②については、山本敬三「民法講義Ⅳ-1」初版521~525頁、岡口基一「要件事実マニュアルⅡ」第6版358頁参照)。
①と②のいずれにおいても、GF間の原賃貸借契約の合意解除を転借人Hに対抗することの可否が問題になります。ここでは、原則として対抗不可であること(613条3項本文)を指摘した上で、Fの賃料不払を理由として「賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたとき」に当たるから、例外として、GF間の原賃貸借契約の合意解除を転借人Hに対抗することができる(同条項但書)ことを指摘すれば足ります。
なお、②については、原賃貸借契約の終了に伴う転貸借契約の終了時期や、転借人に対する賃料支払の催告の要否などは問われていないと思われます。
小問(2)①では、受働債権の差押え後に取得した債権を自働債権とする相殺の対抗可能性(511条1項、2項)が問われています。
解答に当たっては、「差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできない」(511条1項前段)との原則論を示した上で、511条2項本文による対抗可能性について論じることになります。その際、511条2項本文の趣旨に遡り、「差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるとき」についての解釈を示した上で、当てはめでは、両債権の発生原因が異なることを踏まえながら相殺への合理的期待が認められるか否かを検討することになります。
小問(2)②では、賃料債権が差し押さえられた後に賃貸人が賃借物を譲渡したことにより賃貸借契約が終了した場合において、差押債権者が第三債務者である賃借人から当該譲渡後に弁済期の到来する賃料債権を取り立てることの可否が問われています。
判例(最三小判平成24年9月4日)は、賃料債権の差押え後に賃貸人(所有者)が賃借人に賃借物を譲渡したために混同(520条本文)により賃貸借契約が終了したという事案において、「賃料債権の差押えを受けた債務者は、該賃料債権の処分を禁止されるが、その発生の基礎となる賃貸借契約が終了したときは、差押えの対象となる賃料債権は以後発生しないこととなる。したがって、賃貸人が賃借人に賃貸借契約の目的である建物を譲渡したことにより賃貸借契約が終了した以上は、その終了が賃料債権の差押えの効力発生後であっても、賃貸人と賃借人との人的関係、当該建物を譲渡するに至った経緯及び態様その他の諸般の事情に照らして、賃借人において賃料債権が発生しないことを主張することが信義則上許されないなどの特段の事情がない限り、差押債権者は、第三債務者である賃借人から、当該譲渡後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることができないというべきである。」として、特段の事情のない限り、差押債権者は賃借人から賃料債権を取り立てることができないと解しています。
本問は、賃借権が対抗要件を備えていないために、賃借物の譲渡に伴って賃貸人の地位が移転せず(605条の2第1項)、その結果、賃借人が新所有者に賃借権を対抗できなくなるという意味において、賃貸人が賃借人に使用・収益させる債務が履行不能となり、「賃借物の全部が…その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった」として、賃貸借契約が当然に終了する(616条の2)ことになるという点において、判例の事案とは異なりますが、「賃料債権の差押え後に賃貸人が賃借物を譲渡したために賃貸借契約が終了し、それ以降の賃料債権が発生しなくなった」という本質部分は共通しているため、判例の射程が及ぶと考えられます。
全体
今年の民法は難しすぎます。設問1(1)(2)は短答知識ですし、設問2(1)の②もほぼ実益のない請求であり、勉強する機会は少ないです。設問2(2)②は、平成24年度重要判例解説(事件8)には掲載されているものの、短答試験ですら出題されていない細かい判例です。論文知識レベルの出題は、設問2(1)の①と設問(2)①くらいです。ここまで問題が難しく、細かい知識を問う設問が多いとなると、理想解よりも、現実解を通じて現実的な合格水準を把握することの方が重要であると考えます。
<理想解>
<現実解>
特に参考にしていただきたいのは、設問1(1)(2)と設問2(2)②です。
設問1(1)(2)は、基礎応用完成テキストにも総まくり論証集にも論文知識として論証を掲載していますが、マイナー分野である上に事例や理論面も複雑であるため、論文知識としてちゃんとおさえている受験生は多くないと思います。もっとも、短答知識としても勉強する箇所ですから、合格圏内を競う受験生で解釈の結論すら知らないという人は少ないはずです。論理が飛躍しても構いませんし、多少不正確でも構いませんから、最低限、抽象論を示しましょう。現実解の抽象論はかなりシンプルですが、これでも合格水準です。
設問2(2)②の判例知識を事前におさえていた受験生は非常に少ないと思いますが、問題の所在と結論の方向性くらいは掴めるはずです。そうであれば、問題の所在に従って、求められている結論を導くための抽象論をその場ででっち上げましょう。民法は、現場思考問題が出題されることも多いため、こうした対応力を身に付けておくことが非常に重要です。
商 法
設問1
小問(1)は、平成28年司法試験設問1(1)(解職対象取締役に対する招集通知を欠いた事案)の類題です。
瑕疵ある取締役会決議は原則として無効である(最二小判平成28年1月22日)ことを簡潔に指摘した上で、本件解職決議の瑕疵の有無を検討することになります。
参考答案では、①解職の議題が取締役会の招集通知に記載されていない点、②議長Bが解職対象であるAを退席させた点、③Aと意見対立しているBが議決に加わった点、④定足数・多数決要件の4点について言及しています。
① 問題文には「Bは、Aを代表取締役から解職する旨の緊急の動議を提出し」とあるため、Aを代表取締役から解職する旨の議題は取締役会の招集通知(366条)に記載されていなかったことになります。そのことを指摘した上で、取締役会の招集通知には議題を記載する必要がないことを簡潔に論じるべきです。平成28年司法試験設問1(1)でも同じ論点が出題されています。
② Aが議決にも審議にも加わっていないので、369条2項違反という瑕疵との関係で、特別利害関係取締役に関する論点が問題となっているわけではありません。仮にAが議決又は審議に参加することができるのであれば、BがAを退席させたことが決議の瑕疵に当たるという意味において、㋐代表取締役は自己の解職議案について「特別の利害関係を有する取締役」に当たるか(最二小判昭和44年3月28日)、㋑特別利害関係取締役は審議からも排除されるべきかの2点が問題となります。私の答案では、㋐と㋑のいずれも肯定して、議長Bが解職対象であるAを退席させた点も決議の瑕疵に当たらないとしています。
③ 蛇足かもしれませんが、念のため、Aと意見が対立している代表取締役Bが議決に加わった点が369条2項違反とならないかについても、軽く言及しています。もっとも、代表取締役の解職議案は、不祥事案などを除けば、反対派の代表取締役・取締役から提出されるのが通常であることからしても、Bが「特別の利害関係を有する取締役」に当たる余地はないと思われます。実際、平成28年司法試験設問1(1)の出題趣旨・採点実感でも、代表取締役社長の解職議案が反対派である代表取締役専務から提出された事案において、反対派の代表取締役専務が議決に加わった点について言及するべきとの指摘はありません。
なお、採点実感では、不良の答案の例として、「④代表取締役から解職されたAと対立していたことを理由として、Bについてのみ特別の利害関係を有する取締役に当たるか否かを論ずるものなどが、それぞれ一定数見られた。」とありますが、この記述が、Bが特別利害関係取締役に当たるか否かを検討すること自体を批判する趣旨であるのかは定かではありません。
④ 最後に、決議の瑕疵がないとして本件解職の有効性を認めるのであれば、Aが特別利害関係取締役に当たることと、Eが棄権したことを踏まえて、定足数及び多数決要件(369条1項)を満たすかについて、簡潔に論じるべきです。
小問(2)は、平成28年司法試験設問1(2)と酷似しています。
議論の前提として、①株主総会では取締役全員の報酬総額の最高限度額を定め、最高限度額の枠内における取締役ごとの報酬額の決定を取締役会に一任することの可否について論じます。その上で、②取締役会決議による取締役の報酬減額の可否について丁寧に論じます。
②では、報酬減額には取締役の同意が必要であるとの見解に立った上で、本件報酬決議に関する事情を適切に評価して、代表取締役解職に伴う70万円までの減額については同意があるが、70万を下回る減額については同意がないことを正確に指摘する必要があります。
設問2
設問2は、平成19年司法試験設問1の類題です。
新株発行無効の訴えにおいて、支配株主の異動に関する特則(206条の2)が問われており、同条4項の株主総会の招集通知(299条)に関する瑕疵を論じることになります。
※ 平成19年当時は、206条2が法定されていなかったため、同年の出題の趣旨・ヒアリングには、206条の2に関する言及はありませんが、平成26年改正会社法を前提とした場合には、平成19年司法試験でも206条2違反が問題となります。加藤ゼミナールの過去問講座でも、206条2違反を取り上げています。
本件通知①は206条の2第1項の要件を満たす一方で、本件通知②により、同条4項が適用され、「株主総会の決議によって、当該特定引受人に対する募集株式の割当て…の承認を受けなければならない」ことになります。株主総会を開催するに当たり、株主に対して招集通知を発する必要があるところ(299条1項)、Bが株主名簿上の旧住所に宛てて招集通知を発したこと自体は「株式会社が株主に対してする通知…は、株主名簿に記載…した当該株主の住所…にあてて発すれば足りる」とする126条1項に従ったものですから、招集手続の瑕疵に当たりません。なお、平成28年予備試験では、126条4項が出題されているため、今後も126条が出題される可能性があります。
他方で、「Bは、Aの現在の住所は新住所であることを認識していたものの、Aが本件総会に出席するのを防ぐために、甲社の株主名簿に記載されているAの旧住所に宛てて招集通知を発した。」という事情からすると、株主に出席等の機会を与えるという招集手続の趣旨に照らして、招集手続の瑕疵を認めるべき事案であることが分かります。この問題意識は、平成19年司法試験設問1でも、代表取締役社長Aが、議案に反対することが予想される反対派であるBらが海外に出張しているタイミングを見計らって招集期間内に取締役会の招集通知を発したという事案において出題されています。同じ問題意識を、株主総会の事案を通じて再度出題しているわけです。
” 本件では、募集株式の発行に関する取締役会決議はB派の取締役が海外出張中に行われたので、かかる取締役会決議の効力が問題となり得る(出題の趣旨)。”(平成19年司法試験の出題趣旨)
最後に、206条の2第4項の株主総会の招集手続に瑕疵があったことが支配株主の異動を伴う新株発行の無効原因に当たるかについて、支配株主の異動を伴う新株発行では株式が引受人から第三者に譲渡される可能性が定型的に低いという特殊性を踏まえながら論じることになります。
なお、支配株主の異動を伴う募集株式の発行等では、あくまでも募集事項の決定は取締役会で行い、206条の2第4項の要件を満たす場合には募集株式の発行等について株主総会の承認を得ることを要にするにとどまるため、有利発行や非公開会社における募集株式の発行等とは異なります。こうしたことを踏まえ、吸収説に言及する実益は低いと考え、私の答案では吸収説には言及していません。
<理想解>
<現実解>
設問1(2)と設問2については、理想解と比べて大きな変更点はありません。
設問1(1)は、だいぶシンプルにしており、招集通知への議題不記載(問題文には招集手続に関する記載がないため)、Bが「特別の利害関係を有する取締役」に当たるかについては、丸々カットしています。また、自己の解職議案について「特別の利害関係を有する取締役」に当たるかについての論証も若干コンパクトにしており、答案冒頭における瑕疵ある取締役会決議の効力については原則論に言及するにとどめています。
民事訴訟法
設問1
設問1は、自己利用文書(220条の4号二)について論じさせる問題です。
まず注意するべきは、立論の方向性が決まっていることです。設問では、「Xの立場から、本件予測表が民事訴訟法第220条第4号ニの文書に該当しないとする立論として、どのようなものが考えられるか。」とあるため、自己利用文書該当性を否定する方向で論じる必要があり、それに伴い、「Yからの反論」は、自己利用文書該当性を肯定する方向のものに限られます。立論の方向性が真逆になると、大失点することになります。
判例(最二小決平成11年11月12日)は、自己利用文書の要件は、①内部利用目的・外部非開示性、②不利益性、③特段の事情の不存在の3つであり、これらは「その作成目的、記載内容、これを現在の所持者が所持するに至るまでの経緯、その他の事情」から判断されます。
比較対象となる銀行の貸出稟議書に関する平成11年最判の判断内容からしても、問題文の事情からしても、本問では、①ないし③について満遍なく検討することが求められているのではなく、①を中心に検討することが求められていると考えられます。
①における内部利用目的と外部非開示性は、重なる場面も多いですが、一応別々の要件であるため、内部利用目的が認められる一方で外部非開示性が否定する場合もあり得ます(「民事訴訟法 判例百選」第6版66事件・解説2〔勅使川原和彦〕)。
私の答案では、内部利用目的は認められ得るとする一方、外部非開示性を明確に否定しています。
なお、参考判例として、銀行の自己査定資料の自己利用文書該当性を否定した最二小決平成19年11月30日(平成19年重要判例解説・事件5)があります。本決定は、「相手方は、法令により資産査定が義務付けられているところ、本件文書は、相手方が、融資先であるAについて,前記検査マニュアルに沿って,同社に対して有する債権の資産査定を行う前提となる債務者区分を行うために作成し、事後的検証に備える目的もあって保存した資料であり、このことからすると、本件文書は、前記資産査定のために必要な資料であり、監督官庁による資産査定に関する前記検査において,資産査定の正確性を裏付ける資料として必要とされているものであるから、相手方自身による利用にとどまらず,相手方以外の者による利用が予定されているものということができる。そうすると、本件文書は、専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、外部の者に開示することが予定されていない文書であるということはできず、民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないというべきである」として、①に該当しないとして自己利用文書該当性を否定しています。
設問2
設問2は、相殺の抗弁と重複起訴禁止(142条)に関する出題です。
本件相殺の抗弁のうち、残部債権を自働債権とする部分については、判例(最三小判平成10年6月30日)を踏まえて、①抗弁後行型の場合における相殺の抗弁の主張は142条の趣旨に反すること、②先行訴訟が明示の一部請求である場合に後行訴訟における残部債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張することは142条の趣旨に反しないこと、③②の相殺の抗弁の主張は、特段の事情のない限り、訴訟上の権利の濫用にも当たらず適法であることを論じることになります。判例は、別訴における相殺の抗弁の主張が問題となった事案でありますが、別訴の場合ですら残部債権を自働債権とする相殺の抗弁が許容されているわけですから、反訴の場合にも③の射程は及びます。
本件相殺の抗弁のうち、本訴請求債権を自働債権とする部分は、最二小判令和2年9月11日の判例理論とその射程を正面から問う問題です。最新重要判例であるため、加藤ゼミナールの試験対策メディアでも取り上げています。
議論の前提として、反訴の場合であっても、裁判所が裁量により弁論を分離(152条)して本訴と反訴を別々に審理判断することにより、本訴における請求債権に対する既判力(114条1項)と反訴における相殺の抗弁に供されている本訴請求債権に対する既判力(同条2項)が矛盾抵触する危険が潜在しているから、反訴において本訴請求債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張することは、本来であれば、142条の趣旨に抵触することになる、という点を指摘する必要があります。だからこそ、平成18年最判(最二小判平成18年4月14日)でも令和2年最判(最二小判令和2年9月11日)でも、弁論の分離を禁止するための理論構成が問題となったのです。
平成18年最判では、本訴において反訴原告が反訴請求債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張した場合であったため、反訴原告が相殺の抗弁を主張したことに着目して、反訴が予備的反訴に変更されるという解釈を採用することができましたが、令和2年最判は、反訴において本訴原告が本訴請求債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張しているため、予備的反訴構成を用いることができません。そこで、令和2年最判は、自働債権と受働債権とが「相殺による清算的調整を図るべき要請が強い」関係にあることを根拠にして、相殺の抗弁を認めるべきであるとの価値判断ありきで、弁論の分離を禁止するという構成を採用しました。
令和2年最判は、本訴請求債権と反訴請求債権とが請負契約に基づく請負代金債権と同契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権の関係にある場合(※平成29年改正前民法下の事案)において、㋐「請負契約における注文者の…瑕疵修補に代わる損害賠償債権は、…実質的、経済的には、請負代金を減額し、請負契約の当事者が相互に負う義務につきその間に等価関係をもたらす機能を有するものである」ことと、㋑「請負人の注文者に対する請負代金債権と注文者の請負人に対する瑕疵修補に代わる損害賠償債権は、同一の原因関係に基づく金銭債権である」ことを理由に、「相殺による清算的調整を図るべき要請が強いものといえる」として、相殺の抗弁を適法とするために、弁論の分離を禁止しました。
本問では、判例理論の射程について、X債権とY債権について「相殺による清算的調整を図るべき要請が強いものといえる」か否かという観点から論じることになりますが、㋐や㋑に準ずるような事情もないため、弁論の分離を禁止するべきほどに「相殺による精算的調整を図るべき要請が強い」とは認められません。したがって、判例の射程は及ばず、弁論の分離を禁止することはできない。
そうである以上、本件相殺の抗弁のうち、本訴請求債権を自働債権とする部分は、弁論が分離されて同一債権について既判力が矛盾抵触する危険が残るため、142条の趣旨に反し、不適法となります。
今年の民事訴訟法は、全体的に過去問との関連が強い問題であったといえます。設問1の自己利用文書は、令和1年司法試験設問3で出題されており、設問2における最三小判平成10年6月30日は平成25年司法試験設問3、平成24年予備試験設問1、令和2年予備試験設問2で出題されています。また、設問2における令和2年最判(最二小判令和2年9月11日)は出題されていませんが、令和2年最判を理解する前提となる平成18年最判(最二小判平成18年4月14日)は、平成27年司法試験設問1で出題されています。
<理想解>
<現実解>
全体的に、一つのひとつの論述をコンパクトにしています。設問1では、銀行の貸出稟議書に関する判例について詳細する減給できる受験生はほぼいないでしょうから、反論では、判例の結論にだけ言及しています。設問2では、理論構成や検討事項は同じです(いずれの論点もAランクの超重要論点であるため)が、論証をコンパクトにしています。
刑 法
設問1
設問1では、登記済不動産(山林)の二重譲渡の事案において、①第一譲受人に対する横領罪(252条)の成否、②第二譲受人に対する詐欺罪(246条1項)の成否が問われています。
①については、横領の既遂時期も問われていると思いますが、多論点型の問題であることを踏まえて、「横領」の当てはめの中で既遂時期まで意識した論述をするにとどめています。
②については、第二譲受人は所有権移転登記を取得することで確定的に所有権を取得することができる(民法177条参照)ことを踏まえて、欺罔行為における重要事項性を論じることになります(大塚裕司「応用刑法Ⅱ」初版356~358頁、高橋則夫「刑法各論第5版408~409頁」)。参考裁判例として東京高判昭和48年11月20日がありますが、問題の所在を示した上で問題文の事情も使って自分なりに論じることができれば合格水準であると考えます。
” 不動産の所有者が第一の買主との間に不動産の売買契約を締結し、権利証その他の登記申請に必要な書類を交付している場合において、右買主の登記未了を奇貨として、これを他に売却し、第二の買主に所有権移転登記を経由させたときは、対抗力の取得を目的とする不動産取引の通例にかんがみ、第一の売買を告知しなかつたことは第二の買主の買受行為との間に詐欺罪の予定する因果関係を欠くのを通常とするのであるが、本件のように第二の買主において売買代金を交付し、不動産につき所有権移転請求権保全の仮登記を取得したが、いまだ所有権移転の本登記を取得しないうちに売買契約を解除するに至つたときは、右売買の経緯に照らし、第一の売買の存在およびその内容等が第二の買主の所有権移転登記の取得を断念させるに足りるもので、第二の買主が、もし事前にその事実を知つたならば敢えて売買契約を結び、代金を交付することはなかつたであろうと認めうる特段の事情がある限り、売主が第一の売買の存在を告知しなかつたことは詐欺罪の内容たる欺罔行為として、第二の買主から交付させた代金につき詐欺罪の成立があるものと解するのが相当である。”(東京高判昭和48年11月20日)
設問2
設問2は、実行担当者乙が客体の錯誤と方法の錯誤に陥っているという応用事例です。
乙の罪責では、④客体の錯誤と⑤方法の錯誤を区別して論じることになります。その上で、⑥成立する故意犯の個数についても言及する必要があります。
丙の罪責では、⑦共謀共同正犯、⑧共同正犯関係からの離脱、⑨共同正犯における具体的事実の錯誤が問題となりますが、いずれも簡潔に論じれば足ります。事案からして、⑦を大展開するようなケースではないですし、⑧が認められないことも明らかです。また、⑨の議論では、乙の罪責で論じた④~⑥を流用することになります。
全体
例年と同様、多論点型の問題であるため、重要度を見極めて適切なメリハリ付けをしながら検討事項を網羅することが重要になってきます。
<理想解>
<現実解>
刑法では、とにかく、罪名と論点を網羅することが重要になってきます。本問は、多論点型の問題であるため、抽象論をぎりぎりまで短くし、錯誤論以外では、理由付けを飛ばしています。また、共同正犯関係からの離脱については、おまけの論点にすぎないため、抽象論を飛ばして、当てはめの中で規範を出すという書き方をしています。
刑事訴訟法
設問1
設問1は、保護責任者遺棄罪の訴因について、死体遺棄罪の予備的訴因を追加することの可否が問われています。
少数論点型の問題であるため、基本的事実同一説を論じる際には、「公訴事実の同一性」の趣旨・機能にもちゃんと言及するべきです。その際、参考答案にある通り、機能概念説に立つのが無難です(古江賴隆「事例演習刑事訴訟法」第3版279~280頁)。機能概念説とは別に、二重処罰の実質が生じる事態を回避することに着目する見解もありますが、この見解から基本的事実同一説を導けるのかは定かではありません。
例えば、酒巻匡「刑事訴訟法」第2版302~304頁は、「法が訴因変更に限界を設定している趣旨・目的は、刑事手続による刑罰権(実体法)の具体的実現に際して、別訴で二つ以上の有罪判決が併存し二重処罰の実質が生じるのを回避することにある。「公訴事実の同一性」とは、このような目的のための道具概念と理解することができる。」とした上で、狭義の同一性について、「両訴因の事実の記載を比較したとき、両者が、1回の手続においてどちらか一方で一度だけ処罰すれば足りるかという観点から、両立し得ない択一関係にある場合である。すなわち、仮に別訴で両者が有罪とされれば実質的に二重処罰となり不当というべき関係が認められる場合である。」として、判例の基本的事実同一説ではなく、非両立性基準を全面に出して判断する見解を採用しています。また、古江賴隆「事例演習刑事訴訟法」第3版289頁・41)でも、二重処罰の実質が生じる事態を回避すること云々という説明について、「この箇所は、酒巻302頁によったものであるが、判例の採る基本的事実同一説の理由付けとして用いることができるかどうか、疑問がなくはない。基本的事実同一説の理由付けについては、判例は何も述べておらず、明確とはいえない。」とあります。
基本的事実同一説を使った当てはめの仕方(特に、共通性基準と非両立性基準の関係)については、試験直前の法律コラムでも詳細に取り上げているので、そちらもご確認ください。
なお、令和1年司法試験の採点実感でも言及されていることですが、裁判所が訴因変更請求を許可するに当たり、訴因変更が必要であることは要件とはなりませんから、平成26年司法試験設問2のように検察官の主張・立証方針の一環として訴因変更の可否が問題となっているような特殊なケースを除き、訴因変更の可否の前提として訴因変更の要否についてまで論じる必要はありません。
設問2
設問2は、裁判所が、遺棄した時点において、Vが生きていたか死んでいたかが明らかではないとの心証を得て、甲に死体遺棄罪が成立すると認定して有罪の判決をすることの可否を問う問題です。
メイン論点は『秘められた択一的認定』ですが、理論上は、保護責任者遺棄罪と死体遺棄罪とが包摂・被包摂の関係にあるのであれば予備的認定が可能であるため、札幌高判昭和61年3月24日でも控訴趣意として予備的認定の可否に言及されていることも踏まえて、『予備的認定』についても言及しています。
『予備的認定は、2つの犯罪事実の間に包摂・被包摂の関係が認められる場合に許容されるものであるところ、保護責任者遺棄罪と死体遺棄罪との間には包摂・被包摂の関係を認めることはできませんから、『予備的認定』を否定した上で『秘められた択一的認定』を論じ、『秘められた択一的認定』として、裁判所が甲に死体遺棄罪が成立すると認定して有罪の判決をすることを認めることになります。
なお、本問では、裁判所が「保護責任者遺棄罪又は死体遺棄罪である」として明示的に択一的認定をすることの可否は問われておらず、「死体遺棄罪である」と認定することの可否だけが問われているため、『明示的択一的認定』の可否について言及する必要はありません。
<理想解>
<現実解>
今年の刑事訴訟法は、論じるべきことが少ないため、正解筋を外さなければ、2枚でも合格答案になります。特に、設問1では共通性基準と非両立性基準の関係を正しく理解した当てはめをすることができるか、設問2では秘められた択一的認定の可否に先立って予備的認定の可否を論じることができているかという、論述の質で大きな差が付きます。
また、コンパクトに論じるとはいえ、少数論点型の刑事訴訟法では、一言でも構いませんから、論証の理由付けは書くべきです。例えば、「公訴事実の同一性」の判断基準について。令和1年司法試験の出題趣旨・採点実感では、「公訴事実の同一性」の趣旨・機能について言及するようにとの指摘があります。
労働法
設問1
設問1は、主として、労基法上の労働時間該当性が問われており、①「午前11時30分の営業開始前の準備のための時間及び午後9時30分の営業終了後の片付けのための時間」については、最一小判平成12年3月9日(三菱重工長崎造船所事件)を踏まえて、②「休憩時間とされていた午後2時から午後5時までの間」については、最一小判平成14年2月28日(大星ビル管理事件)を踏まえて論じることになります。
問題文には、①に関する事情が少ないため、②のほうが配点が大きいと考えられます。したがって、②をメインで論じ、問題文の事実を使い切る気持ちで当てはめをするべきです。
①及び②の労働時間性を認めた後は、㋐「1時間分の通常の労働時間に対する賃金」の請求と、㋑「3時間分の労働基準法第37条所定の割増賃金」の請求について論じることになります。ここでは、㋐と㋑を区別した上で、最一小判平成14年2月28日(大星ビル管理事件)を踏まえて論じることになります。
厄介なのが、㋐と㋑の内訳です。厳密には、㋐のうち30分が「午前11時から午前11時30分までの準備時間」(①の前半)、残り30分が「休憩時間とされていた時間のうち午後2時から午後2時30分まで」(②の一部)、㋑のうち2時間30分が「休憩時間とされていた時間のうち午後2時30分から午後5時まで」、残り30分が「午後9時30分から午後10時までの片付け時間」(①の後半)という整理になるはずです。しかし、これだと、㋐と㋑とで判断枠組みが異なるにもかかわらず、㋐と㋑に性質の異なる2つの労働時間が混在することになるため、理論構成が複雑になります。そこで、書きやすさを重視するために、正確性を犠牲にして、㋐=①、㋑=②という整理をしています。
設問2
設問2は、定額残業代制度における対価性に関する判例理論を正面から問う問題です。最一小判平成30年7月19日(日本ケミカル事件)は、重要判例を重点的に出題する近年の予備試験の傾向を踏まえると、今年の出題のヤマの一つでした。加藤ゼミナールの試験対策メディアでも取り上げている労働法の超重要判例です。
定額残業代制度による割増賃金の支払に関する要件は、①通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができること(これを「判別要件」という。)と、②割増賃金に当たる部分が法定計算額以上であること(これを「割増賃金額要件」という。)の2つであると理解されていました(高知県観光事件・最二小判平成6年6月13日等)。
もっとも、近時の判例は、①判別要件を判断するための前提として、⓪使用者側が割増賃金として支払ったと主張している賃金部分が時間外労働に対する対価として支払われるものといえること(これを「対価性要件」という。)が必要である旨を明示しており、事案の違いを通じて対価性要件を肯定したものと否定したものに分かれています(肯定:最一小判平成30年7月19日・日本ケミカル事件、否定:最一小判令和2年3月30日・国際自動車事件)。
事案によっては、判別要件の前提として対価性要件を論じる実益のないものもあります(例えば、平成20年司法試験第1問、令和2年司法試験第1問)が、令和7年予備試験では、対価性要件がメイン論点として問われています。ここが、これまでの司法試験過去問との違いであり、最新重要判例まで勉強していたかどうかで大きく差が付くポイントであるといえます。
<理想解>
<現実解>
予備試験の 選択科目の合格水準が基本7科目に比べて低いことも踏まえて、現実解ではだいぶ水準を落としています。
設問1では、①準備・片付けをしていた各30分の労働時間性、②休憩時間とされている3時間の労働時間性、③通常の労働時間に対する賃金請求権と時間外労働に対する割増賃金請求権の有無が問われているところ、①については、下位基準には言及していません。本問において、①の結論は明白であり、かつ、当てはめで使える問題文の事情も少ないため、メイン論点であるのか不明であるからです。また、③については、そもそも問われているのかすら怪しいので、論点としての何度も踏まえて、丸々カットしています。他方で、②はメイン論点であり、当てはめで使う事情も多いので、判例に従った論証をした上で、問題文の事情を使い切るくらいの気持ちで当てはめをしています。
設問2では、定額残業代制の論証はしっかりと書いていますが、対価性について充実した当てはめができる受験生は少ないため、支払の対象となる時間外労働の時間数に関する記載・説明がないという事情を強調するだけで対価性を否定しており、勤務状況との乖離という点については言及していません。
経済法
<事案の整理>
以下の表のように年度別の入札ごとに事前会合を行っているため、それぞれの事前会合を自分なりに法的に整理して分析できたか否かがポイントになると考えられます。
事案については、郵便区分機談合事件(東京高判平成20.12.19・百23)を参考にしたものと考えられますが、主要な事実関係に改変が認められるうえ、同事案を学習していた受験生は多くはないと考えられるため、判例を知っていたか否かで差がつくような問題ではありません。
なお、郵便区分機談合事件(東京高判平成20.12.19・百23)は、本問題における令和3年5月に行われたようなY1、Y2間で事前に情報の開示を受けたもののみ落札する旨の意向を交換するような会合の認定は行われなかった事案であり、明確に事前の連絡・交渉が認定できない場合にも、黙示の意思連絡が認定できるのかが問題になりうる事案でした。
| R3入札 | 事前
会合 |
・Aが事前に購入計画等の情報をY1及びY2に開示 ・Y1:「情報提示を受けた甲以外の入札には参加しない予定である」 ・Y2:「令和3年度に予定されている甲の指名競争入札においては、情報提示を受けた甲についてのみ入札に参加する見込み」 |
| 入札 |
・2社は、自己が情報提示を受けたもののみ入札参加 ・落札率99.7%を下回ることはない。 |
|
| R4入札
R5入札 |
事前
会合 |
・R4以降の発注に関しても事前に情報提示を受けられるようAに要請することを合意 ・情報提示を受ける都度、会合を開催して情報提示の有無を確認し合う |
| 入札 |
・R3年の入札と同様、自己が情報提示を受けたもののみ入札参加 ・落札率等の状況はR3入札と同様であり、R3入札~R5入札にかけて2社の受注額は、Aの総発注額のおおむね半分ずつ |
|
| R6入札 | 事前
会合 |
・Aが指名競争入札から一般競争入札に変更する旨方針転換 ・Aに対して、2社が協力して一般競争入札の導入に反対し、情報提示の継続を要請することを決定 ・それぞれ上記決定に従い、Aに要請したが、断られたため、入札に当たって会合を開催しないことにした。 |
| 入札 |
・Y1、Y2に加えて、新たにY3が参加 ・落札率は65%から80% |
<解答の方針>
1. 共同して
(1)R3入札について
ア. 規範
規範については、多摩談合事件(最一小判平成24.2.20・百20)を参考にした規範を記載したうえで、談合における意思の連絡の対象は、個別調整ではなく、基本合意であることを確認する必要があります。
また、会合で「情報提示を受けた甲以外の入札には参加しない予定」という点を確認した点は、各社の入札の方針を確認しただけにすぎないため、明示の合意とまではいえず、黙示の合意の成否を検討することになると考えられます。
イ. 本問の特殊性
本問では、当事者が2社のみであり、そのうち1社しか入札に参加しないため入札毎に入札価格の連絡を行う等の個別調整に係るやりとりが不要な事案であり、問題文に個別調整に係るやりとりは現れません(例えば、談合が出題された平成26年第2問では、15社の談合当事者が、物件ごとに、指名業者の確認、受注希望者の確認、受注予定者の決定、入札価格にかかる連絡等の個別調整に係るやりとりが存在します。)。
したがって、過去問で出題された事案のように個々の入札における個別調整に係るやりとりそのものを基本合意を推認するための間接事実とみることはできません。
もっとも、個別調整に係るやりとり自体はなくとも、入札に係る結果(どちらか一方が事前にAから情報の開示を受けた入札にしか参加していないこと、落札率の異常な高さ等)や事前の情報交換において、Aから情報の開示を受けたものしか入札しない旨の意向を確認し合っていたことからすれば、「入札については、Aから情報の提示のあった当該物件の入札にのみ参加し、情報の提示のなかった者は、当該物件の入札に参加しないことにより、相手方が入札できるよう協力する」旨の黙示の意思連絡が認められる事案といえます。
ウ. 合意の対象
Y2の発言が、「令和3年度の入札において」との限定をつけている点、令和4年以降もAから情報の開示がなされるかどうかは令和3年の時点では不透明であったこと等からすれば、R3入札前に成立した黙示の合意の対象は、R3入札に限定した合意と認定させたい問題のように見えます。
他方で、R3以降の入札も含めて、すべての入札が対象となる合意がR3入札の前の時点で成立していたと認定することを否定するような事情もなく、両論あり得るように考えられます。
(2)R4以降の入札について
ア. 黙示の合意の成立
令和3年10月の会合で共同してAに情報開示の要請を行う旨合意をし、実行している点やR6の発注方法の変更にあたって、共同して異議を述べる旨決定している点、入札結果の点等から、令和4年以降も継続してR3と同様のルールに従い、調整を行う旨の黙示の合意が成立していたと考えられます。
イ. 合意の終了時期(R6以降の入札について)
事業者間で合意が破棄された場合には合意が消滅する(東京高判平成22.12.10・百32)ところ、R6入札では、Aから事前の情報入手ができなくなり、入札に当たって会合を開かず、従前通りの個別調整行為は行われていないため、合意が破棄されたとみることができると考えられます。
入札の方式も一般競争入札に変更となり、Y3も新たに参加し、落札率も従前とは異なっている点も、R6入札が過去の入札と性質を異にするものであることを基礎付けると考えられます。
したがって、R4以降の入札に係る合意については、R6入札が開始される前の時点で合意の破棄により終了しており、R6入札は合意の対象には含まれないものと考えられます。
2.「競争を実質的に制限する」
規範については、多摩談合事件(最一小判平成24.2.20・百20)を参考にした規範を記載できることが望ましいです。
2社が指名業者の100%を占めること、落札率等の落札の結果に係る事情があるので、当該事情を利用して事実認定することになると考えられます。
3.「公共の利益に反して」
2社からは、事前に発注者たるAが落札者に係る意向を示しており、それに忖度したに過ぎないから行為は正当化され、「公共の利益に反しない」との主張が行われるかもしれません。
もっとも、上記のような談合行為は当事者らの利益率が上がるのみであり、消費者の利益につながらないことは明らかであるため、発注者側の関与をもって正当化事由と考えることはできないと考えます(菅久「独占禁止法」60~61頁も参照)。
本問では、事前の連絡・交渉がある事案であるため、裁判例の事案に比して黙示の意思連絡の認定が比較的容易な事案です。
なお、発注者の関与を「公共の利益」で検討すべきことを求めているかどうかまでは、出題趣旨が公表されていない現段階では判断することができず、記載としては不要な可能性もあります。
倒産法
設問1
設問1では、別除権付破産債権者の権利行使の方法(別除権の行使及び破産債権の行使)が問われています。別除権付破産債権者の権利行使は、平成22年司法試験第1問、平成28年司法試験第1問、平成30年司法試験第1問及び令和4年司法試験第1問でも出題されている頻出分野です。特に、平成22年司法試験第1問及び平成28年司法試験第1問が参考になるかと思います。なお、倒産法速修テキストの【演習問題6】でも同種の問題を取り上げています。
小問(1)では、B銀行による担保不動産競売手続開始の申立ての可否が問われています。
この点、「別除権は、破産手続によらないで、行使することができる」(破65条1項)ので、本件抵当権が「別除権」に該当すれば、B銀行による上記申立ては認められることになります。そこで、本件抵当権が「別除権」に該当するかどうかを、破2条9項に照らして判断することになります。
小問(2)では、B銀行による破産債権の行使の可否が問われています。また、設問には「破産債権の届出事項にも留意しつつ、説明しなさい」との指示があるため、別除権付破産債権者は届出に当たり、何か特別なことをしなければならないのでは?と分析したいところです(もちろん、知識を持っておくに越したことはありません。)。
まず、前提として、B銀行が別除権付破産債権者であることを示しましょう。具体的には、本件貸金債権が「破産債権」(破2条5項)に該当することを指摘します(なお、小問(1)でB銀行が別除権を有していることを指名しているので、この点は指摘しなくても大丈夫かと思います。)。
次に、別除権付破産債権者の破産債権の行使については、不足額責任主義(破108条1項)が適用されることを示します。この条文をあげることは必須かと思います。
その上で、別除権付破産債権者の破産債権の届出には、+αの事項を届け出る必要がある(破111条2項)旨を示してきます。この破111条2項ですが、事前の知識がなくても、設問の「破産債権の届出事項にも留意しつつ」との指示から、目次を開いて、「第4章 破産債権」「第2節 破産債権の届出」を見つけ、破111条以下を検索し、別除権付破産債権者に関する条文はないかと逐一条文を見ていくことで辿り着くことができるものと思われます。
設問2
設問2では、破産手続開始決定と係属中の訴訟手続が問われています。こちらも、平成19年司法試験第1問、平成21年司法試験第2問、平成24年司法試験第1問及び令和2年司法試験第1問と、4回ほど出題されている頻出分野です。
ただ、本問は、破産債権に関する訴訟であり、その意味では過去に出題がなされていないものともいえます。
破44条1項の中断に触れることは必須で、受継の問題や訴訟の終了等まで触れられたか否かで差が付く問題かと思います。特に②の訴訟については、破127条の受継の申立てについて触れられたかどうかで差が付くものと思われます。
設問3
設問3は、これまでに問われたことのない問題でした。また、設問1及び設問2では破産法について問われていたのに対し、設問3で急に民事再生法が問われたため、面食らった受験生の方々も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
この問題は、まず適切な条文を指摘できたか(①は民再26条1項1号、②は39条1項)がポイントです。ここである程度差が付いてしまうように思います。次に、条文の要件を丁寧に認定したかがポイントです。さらに、①では民再26条1項の「必要があると認められる」ときについて何らかの解釈を示し、問題文の事実を摘示・評価し、結論を導くことができたか、②では中止(民再39条1項)に触れるだけにとどまらず、その後中止した破産手続がどうなるのかについてまで触れられるかことができたかがさらなるポイントかと思います。
民再26条1項の「必要があると認められる」ときの解釈について、私の答案は、佐村浩之・内田博久「リーガル・プログレッシブ・シリーズ 民事再生」114頁に記載のものを用いていますが、現場ででっち上げてしまえば十分かと思います。試験現場の思考過程としては、民再26条1項で先行する手続を中止できるのは何故?→後で開始決定がなされる再生手続に悪い影響を与えてしまう可能性があるからじゃないか?→じゃあ、そういう規範を立てよう→先行する手続を中止しないと、再生手続が害される可能性がある場合には、「必要があると認められるとき」に当たると解する、という規範を立てればよい、というものが一つあり得るかと思います。
なお、民再26条1項の「必要があると認められる」ときの具体例として、才口千晴・伊藤眞監修「新注釈民事再生法【上】」第2版126頁は、「破産手続が先行することにより事業価値が著しく毀損してしまう場合」を挙げています。これを前提にすると、本件の事実関係では、この要件を満たさないと考えてよいのではないかと思います。もっとも、適切な評価・理由付けがなされていれば、結論はどちらでもいいかと思います。
<参考答案へのコメント>
設問1 小問(1)
設問1 小問(2)
設問2
設問3