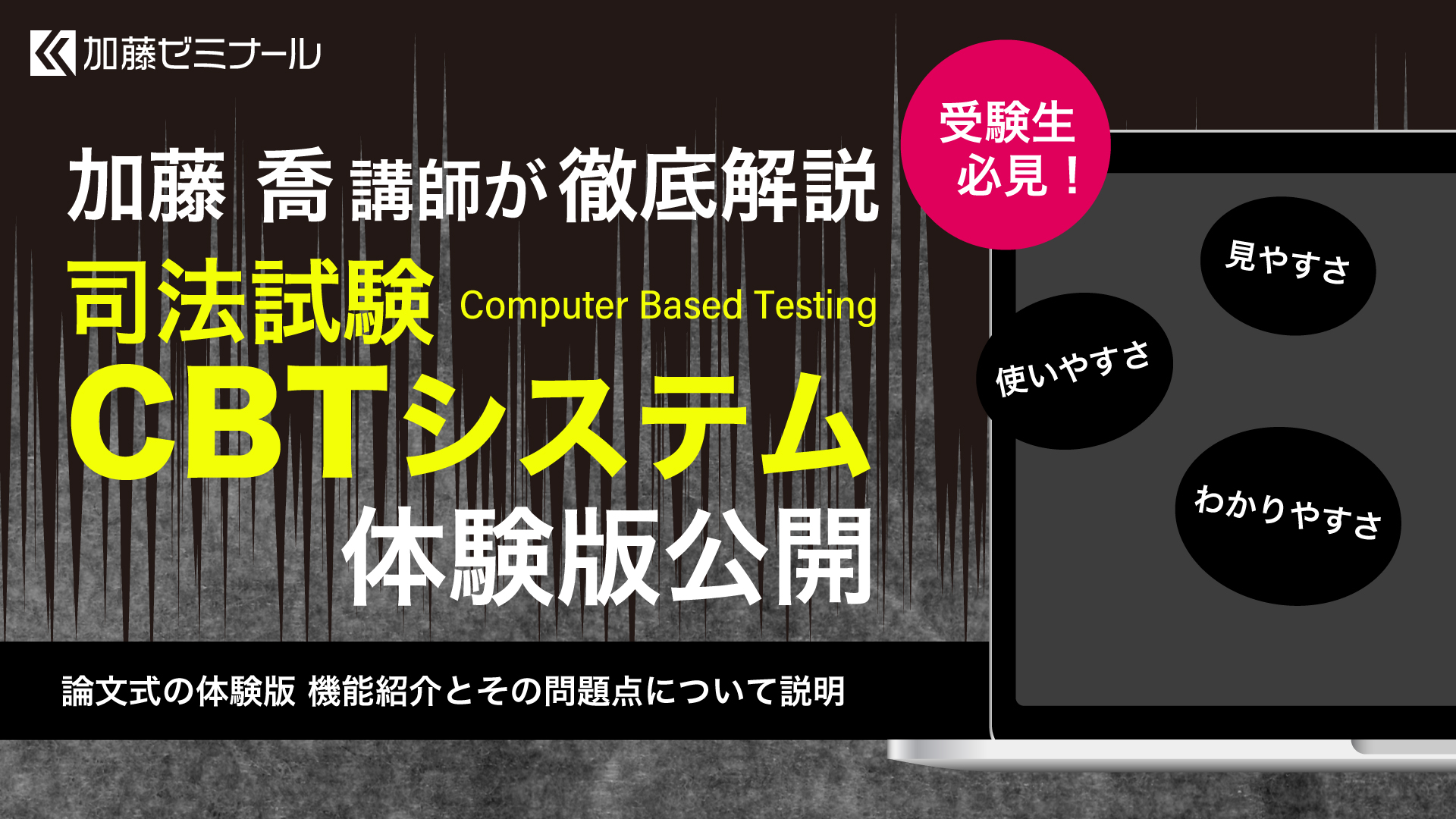
本日、法務表のwebサイトで司法試験CBTシステム(体験版)が公開されました。
→ https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00238.html
短答試験と論文試験の双方について、体験版が公開されていますが、本記事では、論文試験の体験版の機能紹介とともに、その問題点について説明いたします。
.
【問題文】
1⃣左右の余白がないので、余白へのメモ書きはできません。
2⃣問題文のコピーもできません。
3⃣問題文を1ページ(縮小機能を使っても最大2ページ)ずつしか閲覧できないため、特に行政法において個別法と問題文を同時に参照することができないという点が非常に厄介です。
4⃣マークは1行ずつしか引けません。(ドラッグして一気に数行分マークを引くことはできません)。
5⃣戻るボタンがないため、書込みやマークを消す際には、消しゴム機能を使う必要があります。
6⃣問題文ごとに下部にページ数が振られていないので、ページの境界が不明です。左にページ数が表示されますが、それでも不明瞭です。
.
【答案】
1⃣合計8枚、1枚23行、1行30文字、最大5520文字
特に選択科目では、字数が足りなくなる可能性があります。
基本7科目は平均5枚(1行27~28文字)の私でさえ、労働法では1行35文字くらいで4枚目の最後まで書きました(それでも、第1問では紙面が足りませんでした)。
2⃣デフォルトだと答案右端を表示しきれないので、縮小機能を使う必要あります。
3⃣デフォルトだと、23行のうち8行しか表示されません。縮小機能&画面の引伸ばし機能を使えば、23行分表示できます。
4⃣答案内でのコピー&ペーストは可能です。
5⃣条文のコピー&ペーストも可能です。
6⃣問題文のコピー&ペーストはできません。
.
【条文検索】
1⃣他の法令に移動した場合、その前に閲覧していた法令の画面の位置はリセットされます。
例えば、民法100条の参照途中で他の法令に移動し、民法に戻ると、民法の一番最初の画面(民法の目次の一番最初)が表示されます。
2⃣条文単位でのブックマーク機能があります。
上記1⃣の問題があるため、他の法令に移動する際にはブックマークを使うことになります。
3⃣英数字による検索はできません。
検索機能では、条文番号だけでなく、目次、条文の見出し、条文の本文にも対応しています。
しかし、条文番号も含めて数字については、漢数字でなければ検索にヒットしません(例えば、100条と入力しても100条には移動しません)。
.
【構成用紙】
1⃣デフォルトでは表示されず、構成用紙ボタンを押すと表示されます。
2⃣問題文、構成用紙、答案を同時に閲覧することはできません。
構成用紙の表示方法は「左配置」「全画面」「右配置」の3つですが、「左配置」だと問題文が丸々隠れる(問題文にかぶさる形で構成用紙が表示される)、「全画面」だと問題文も答案も見えない、「右配置」だと答案が見えないです。
3⃣上記の2⃣の致命的欠陥があるから構成用紙を使う機会はほぼないです。
おそらく、構成用紙に構成を入力するのではなく、『答案用紙に直接構成を入力して、その構成に肉付けする形で答案作成を進める』という方法が主流になると思われます。
.
【入替え機能】
1⃣問題文(左全部)、条文(右上)、答案(右下)の並びを入れ替えることができるが、使うことはまずないと思います。
.
今回公開された司法試験CBTシステムの体験版は、機能面の不備・欠陥が多い上に、司法試験(及び予備試験)のCBT化の目的や実務の現状からかけ離れた仕様になっています。
CBT化の主眼は、手書きでの大量の答案作成が時代遅れであり実務の実態にも合っていないことや、手書きだと判読困難な答案が生じることに適切に対処することにあります。
こうした目的との関係では、デジタル化は「答案作成」に限れば十分であり、かつ、「問題文」「条文」「構成用紙」までデジタル化したことにより上記のような様々な不便が生じることも踏まえれば、「問題文」「条文」「構成用紙」はむしろ紙媒体によるべきであるといえます。
また、実務では、パソコンを使って書面を作成しますが、訴訟関係書類などまでデジタル化して閲覧している人は限られますし、その場合でも複数のモニターを使用することにより一覧性などが低下することのないよう適切な工夫がなされています。
受験生、合格者、実務家といった関係者からヒアリングをしたり、十分な利便性の検証もしないまま、体験版の作成を進めた結果です。
今の体験版のままでは、受験生の実力を適正に図ることができません。これは、法曹を選抜するための試験を歪めることになります。
デジタル化は「答案作成」に限り、「問題文」「条文」「構成用紙」これまで通り紙媒体にするべきです。100歩譲っても、「問題文」と「構成用紙」は紙媒体を維持するべきです。
法務省は、CBT化の目的として「コスト負担」も掲げていますが、受験生は高額な受験料を支払っているのですから、CBT化の目的として紙媒体による「コスト負担」を掲げることは、詭弁という他ありません。
受験生の実力を適正に図ることができる試験制度を維持するために、今回公開されたCBTシステムが適切に改修されることを強く願います。
.
司法試験等CBTシステム(体験版)
https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00238.html